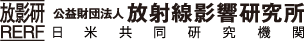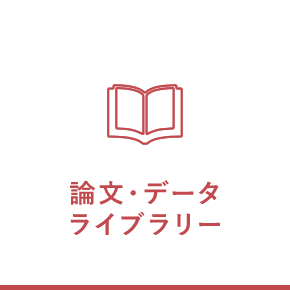肝癌と肝炎との関連性調査
日本ではBおよびC型肝炎の感染は肝細胞癌と密接に関係付けられているため、原爆被爆者の癌部および非癌部の肝細胞におけるDNAレベルでの詳細なウイルス調査が放影研の研究者によって行われている。
放影研放射線生物学部 水野照美、瀬山敏雄、秋山實利
この記事は RERF Update 6(3):6-7, 1994に掲載されたものの翻訳です。
一般の日本人集団よりも原爆被爆者においてより高い頻度で発生するがんが数種類ある。がんは幾つもの段階からなる複雑な過程を経て発生するので、その複雑な局面に放射線がいかに関与しているかを放影研の研究者は調査している。この難題に取組む一つの方法は、電離放射線がもたらした特徴的なDNA損傷として腫瘍中に存在すると思われる様々な遺伝子変化を詳細に解析することである。
なぜ肝癌と肝炎ウイルスの関連を調査するのか
近年、Thompson らにより放影研の寿命調査集団における原発性肝癌(PLC)の発症は有意な線量反応を示すことが報告されている(Radiation Research 137:S17-S67, 1994)。肝癌発生の要因には、B型肝炎ウイルス(HBV)、C型肝炎ウイルス(HCV)、アルコール摂取およびアフラトキシンB1被ばくがある(Harris, Cancer Cells 2:146-148, 1990)。日本国内ではPLCの70%以上がHBVおよびHCV感染に起因することが疫学的研究によって示唆されている。よって肝細胞癌(HCC)における原爆放射線の役割を調査する際、ウイルス感染の頻度を無視することはできない。被爆者の肝癌リスクの増大における放射線の役割を考える上で、被爆者の肝癌に見られるウイルスの解析は何らかの洞察をもたらすかもしれない。
放影研の研究員は放射線被ばくと肝癌の関係に長年注目してきた。ここではその調査の一面を述べる。我々は分子生物学的手法を用いて肝細胞内のHBV感染頻度を解析した。さらにHBVがどのように肝癌発生に関与するか、そしてHBV感染と他の遺伝子変化(発癌の中心的原因と考えられる二種類の現象、すなわち癌遺伝子の活性化、癌抑制遺伝子の不活性化)の間にどのような関係があるのかを調査した。
近年、HBV産物の1つであるHBX蛋白質がp53遺伝子産物に作用してその機能を抑制することが明らかにされた(Wang, Proceedings of National Academy of Science 91:2230-4, 1994)。同様の現象は子宮頚癌において生じており、そこではヒトパピローマウイルスがp53遺伝子機能を不活性化している(Dyson, Science 243:934-7, 1989)。このため肝癌発生におけるHBVの働きはp53不活性化によるのかもしれない。ここで用いた解析方法は、パラフィン包埋した癌部および非癌部肝細胞より抽出したDNAを用いたポリメラーゼ鎖反応(PCR)法である。HBVは3.2キロ塩基対からなるDNAウイルスで、機能を有している3領域(S、pre-CおよびXの部位)をPCR法で増幅した。我々が調べたのはPLC組織237症例および対照となる非腫瘍肝組織396症例である。抽出したDNAの約80%を増幅できた。
肝癌組織のゲノムDNAにおいてより頻繁に見られるHBV
PLC組織と対照組織を比較した場合、HBV感染頻度は対照グループ(3%)よりもPLCグループ(16%)の方が高く、その差は統計的に有意なものであった(表参照)。肝細胞におけるHBVの感染は原因論的にはヒト肝細胞癌に関与し、肝細胞の悪性転化には1つまたは複数の遺伝的事象が必要であることがこれらの所見より推察される。
表. 肝細胞癌症例と対照症例におけるB型肝炎ウイルス感染の頻度、都市および性別
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLC患者におけるHBVの感染頻度は、腫瘍および周辺の正常な肝細胞間ではほとんど差異がない。すなわち、腫瘍細胞がHBVに感染している際には周辺の正常な細胞も感染しており、その逆もまた同様である。居住している都市または性別による明確な差異も同様に認められなかった。
以前に浅野らより、明白な肝疾病を有しない患者(都市と被爆時年齢を一致させた)においてはB型肝炎表面(HBs)抗原陽性率が広島より長崎の方が2倍高いことが報告されている(Journal of National Cancer of Institute 69:1221-7, 1982)。
我々と浅野らとの所見の不一致は、我々が血清中の抗体の有無ではなく肝細胞のゲノムDNA中にウイルス・ゲノムが実際に組込まれている頻度を調べたことに幾分起因しているかもしれない。
放射線被ばくおよびHBV感染
放射線量がHBV感染に対する感受性に何らかの役割をはたしているとしても、その役割はどのようなものであるかは依然不明である。HBV感染と原爆放射線量の相関には傾向があるように思われるものの、統計学的な有意性に達するものではない。より多くの高線量被ばく者の症例を解析すればこの相関の傾向がはっきりするかもしれない。
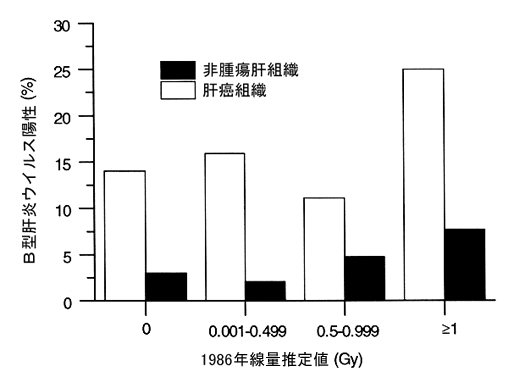
図. 1986年線量推定値別B型肝炎ウイルス感染頻度
被爆者ではEpstein-Barrウイルス(EBV)抗体の線量に依存したより高い力価が秋山らにより観察されているが、このことは被爆者がより頻繁にウイルスに感染するのは原爆放射線により免疫機能が減少したことが原因である可能性を示唆していると思える(Radiation Research 133:297-302, 1993)。
初めて保存組織中に発見されたHCVゲノム
逆転写PCR (RT-PCR)法をパラフィン包埋した肝細胞に用いることで、最近我々はHCVゲノムの発見に成功した。この保存組織中のHCVゲノムの分子解析は長らく研究者が成し得なかったことである。
放射線生物学部では肝癌調査の次の段階において、被爆者の正常および肝癌部組織に検出されるHCVゲノム頻度の調査を試みる。
現在放影研の臨床研究部では、成人健康調査対象者におけるHCVの血清学的研究が行われている。
分子疫学および分子腫瘍学の立場から考えると、ウイルス感染、癌遺伝子および癌抑制遺伝子間の相互作用を理解することで放射線により誘発される肝癌発生機構の全体像をよりはっきり把握することができるかもしれない。