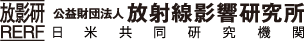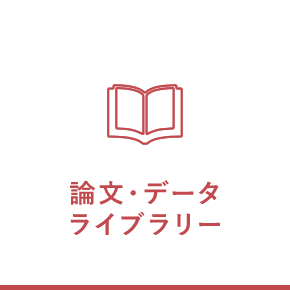放影研の膨大なデータベースは加齢に関する情報の宝庫
2年おきに行われてきた成人健康調査健診の過去30年の累積データは、加齢と様々な健康因子との関係を究明できる資源であり、また、加齢の過程に関するいろいろな調査を計画実施できる、他に類をみない資源である。
放影研統計部 Lennie Wong、臨床研究部 児玉和紀、佐々木英夫
この記事は RERF Update 2(2):4,6, 1990に掲載されたものの翻訳です。
日本および他の多くの工業国が次第に高齢化社会へと向かうに従って、加齢に関連する調査研究が大きく注目されるようになってきた。放影研の研究者は、これまでに放射線による加齢促進の可能性について検討してきた。しかし、これ以外に、ABCC-放影研の臨床部研究員により行われてきた健診から2年ごとに新しい所見が得られており、その30年間におよぶデータベースを有する放影研は、罹患、死亡、臨床検査および生理学的検査測定に関する膨大なデータを用いて、AHS受診者20,000人の生涯を通じての病歴を追跡する他に類をみない機会を有している。日本では、他の研究機関でこのようなデータを得ることは困難である。
非致死的疾患の研究におけるAHSデータの有用性
到命率の高い癌については、その経時的動向は死亡診断書情報に基づいて正確に把握されている。しかし、乳癌、甲状腺癌などの非致死的もしくは治癒可能な癌、また、高血圧、糖尿病、貧血、白内障、胃潰瘍および肝炎といった癌以外の特定の疾患は、死因として記載されることがまれで、その経時的動向および加齢の影響を死亡診断書から正確に知ることはできない。AHSデータについての加齢関連研究を行うことにより、これらの疾患について従来欠けていた発生率情報を得ることができる。AHSで行われている幾つかの診断検査は、潜在的な疾病の発見に有効であるため、疾患探知率が強化され、成人健康調査プログラム全体が加齢関連疾患研究にとっていっそう強固な基盤となっている。
発生率データに対する年齢およびコホートの影響
AHSデータにおける疾患の年齢別発生率を調べることにより、どの疾患が加齢と関連しているか容易にわかる。心臓血管疾患、白内障および骨粗鬆症の発生率は、年齢とともに着実に増加するが、十二指腸潰瘍や甲状腺機能亢進症などの疾患はすべての年齢群にほぼ同様に発生し、年齢との一定した関係は認められない。しかし、これらのデータを検討する際、年齢の影響とコホートの影響を区別することが重要である。
疾患の発生率が年齢とともに全体的に上昇する傾向が認められる場合でも、それは環境の変化に対するコホートの反応のために人為的な差として起こることもあり得る。出生コホート別および他の因子別に適切な層化を行ってみると、その上昇傾向が残る場合もあり、また全く消失する場合もある。典型的な例は椎体骨折であり、これは年齢とともに増加するように見える(図1)。ところが、発生率を10年ごとの出生コホート別にみるとその様子は異なってくる。すなわち、同一年齢でも出生コホート間で発生率に有意な差があり、特に男性においては、追跡期間中に発生率の増加は認められない(図2)。したがって、コホートを考慮せねば誤った結果が得られる恐れはあるが、30年間にわたるAHS追跡調査で種々のコホートについてデータが得られているおかげで、各コホートにおける発生率パターンの経時的変化を検討することが可能である。この情報は、放射線による加齢促進の可能性の調査に有益なだけでなく、特定の疾患に罹患している高齢者の現在および将来の健康管理の指針に組み込むためにも有用である。
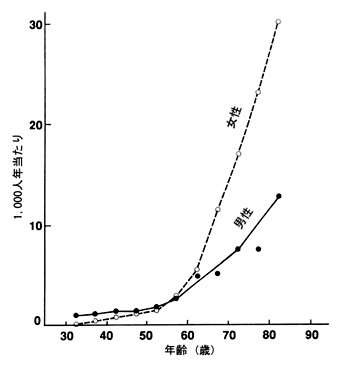
図1. AHSコホートにおける胸椎椎体骨折の発生率(1958-1986年)、出生コホートを考慮しない場合
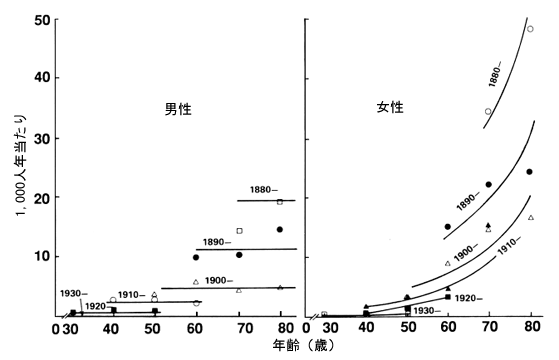
図2. AHSコホートにおける胸椎椎体骨折の発生率(1958-1986年)、出生コホート別
生理学的測定項目と加齢
AHSデータを用いて血清総コレステロール、血圧、心拍数など特定の生理学的測定変数における一生を通じての変化のパターンも調べることができ、加齢過程を別の特異的な観点から見ることができる。
年齢関連変化の評価に横断的データを用いることもできるが、年齢との関連性が個人におけるパターンの変化よりも、むしろ集団間の差の結果として認められることがある。したがって、疾患発生率の場合と同様に、年齢とコホートの影響は交絡するかもしれない。同一対象者の連続測定データを用い、「成長曲線」法などの適当な統計解析を行うことにより、交絡を避けることができる。
1984-1986年の横断的データから得られた男女それぞれの血清総コレステロール値と年齢との関係、ならびに被爆時に 20歳であった人における変化のパターンを 1958年から追跡して得られた関係、この2つの間にみられる違いを 図3 に示した。横断的データの解析では男性に年齢の影響は認められないが、個人についての追跡調査からは明瞭な年齢の影響が認められる。年齢別血清総コレステロール値にも差があることが示唆される。したがって、横断的データの解析では基礎的な関係について誤った印象が与えられる可能性があり、個人の反応およびその変化の経時的パターンの特徴を検討する際には、連続データの使用が望ましい。AHSでは種々の出生コホート(被爆時年齢 0-70歳の範囲)について、13-98歳にわたる連続測定データが得られている。したがって、加齢に関連すると思われる変化のパターンについて広範にわたる検討ができる。
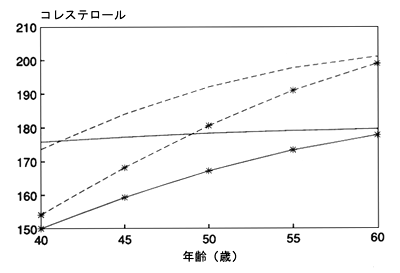
図3. 1984-1986年のデータの横断的解析、並びに被爆時に20歳であった人について、一定の身体質量指標を 0.002として行った成長曲線解析(*で示した曲線)に基づいて得られた男性(実線)および女性(破線)の年齢別血清コレステロール推定値
成長曲線法を用いたこれまでの予備的解析では、血清総コレステロール、拡張期血圧および収縮期血圧の年齢別生涯パターン、並びにこれらの生涯パターンに対する性、都市、出生コホートおよび放射線被ばくの影響を示すことができた。その他の生理学的測定項目に関しても、同様にその関係について検討が行われている。
疾患発生率と生理学的測定データ
長期におよぶ AHS追跡調査のデータを用いて種々の疾患の新たな発生を探知することができ、また、加齢関連疾患の研究においては、特定の生理学的測定変数に関する連続データをリスク因子に含めることができる。AHS対象者から収集したその他の有用な情報としては、アルコール摂取、食習慣、喫煙、出産歴、職業などがあるが、それをすべて組み合わせて、特定の加齢関連疾患に対するリスク因子同定のための調査を計画することができる。
加齢についての計画的調査の機会
臨床研究部の研究員は現在、統計部および疫学部職員の協力を得て、心臓血管疾患や骨粗鬆症などの年齢関連疾患に関する調査研究を行っている。老人性痴呆症や白内障などの年齢関連疾患に関する計画調査が現在計画されているが、これはAHS対象者が平均年齢 61.2歳に達し、このような調査を実施する絶好の機会を提供しているためである。