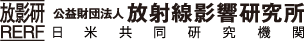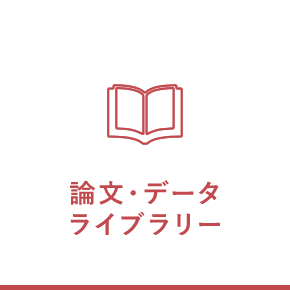小児期に被ばくした原爆被爆者の成長発育
著者の解析結果は、10歳未満での放射線被ばくとその後の成長パターンとの関連性を示唆している。
放影研統計部 大竹正徳
この記事は RERF Update 5(3):3,4,10, 1993に掲載されたものの翻訳です。
原爆傷害調査委員会の成人健康調査(AHS)の一環として、1958年に 約20,000人の原爆被爆者の臨床検診を開始した。AHS検診は現在も行われており、体格を含めた多くの生理学的・生化学的測定値を隔年で収集している。胎内被爆者を対象に様々な時期に記録された身長測定値に関する最近の解析(大竹ら、Radiation Research 134:94-101, 1993)では、妊娠前期および妊娠中期の被爆者に、放射線被ばくと発育遅滞との有意な関連性を認めている。
本調査では、10歳未満の被爆者の発育遅滞を評価した。解析は、第4検診 から 第7検診周期(1964-1972年)に何回か測った身長と体重の測定値に基づいている。原爆時年齢 0-9歳の観察平均身長と観察平均体重を、性別および検診時平均年齢別に区分した後、両市合計した対象者において明確な傾向が認められた(図1)。 図2では市別、性別、1986年線量方式(DS86)線量群別、検診周期年別の身長と体重の観察平均値を示した。DS86線量群別に見ると、広島と長崎間に若干の差異を認めた。性別および検診時平均年齢別の平均身長は、1964-1972年間では変化がないようであった。また、性別および検診時平均年齢別の平均体重は、平均被爆時年齢と共に増加した。
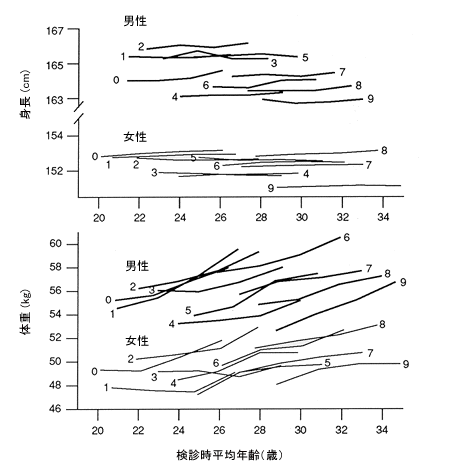
図1. 検診第4-7周期における身長と体重平均値、性別、検診時年齢別、および被爆時年齢別。各線横の数字は副コホート集団の原爆時年齢(歳)を示す。
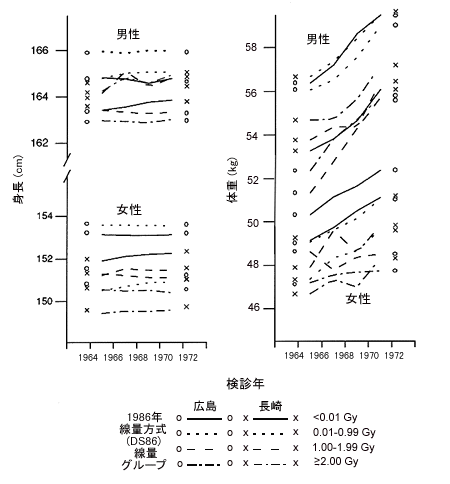
図2. 被爆時年齢0-9歳の対象者の身長と体重の観察平均値
成長曲線分析として知られている統計解析法を用いて、身長と体重および検診時年齢間の関係をモデル化した。男女間で大きな差がある青年期の急成長期を含める複雑なモデル化を避けるために、ほとんどの対象者が成人期の発育成長に到達した(すなわち18歳以上に達した)1964年以降の成長について解析した。第二次成長の異なるパターンは 3歳以前の被爆に依存しているようである。対象者を検診周期別に区分すると、身長と体重の相関は 0.41-0.46 の範囲で有意であった。市、性、DS86線量および被爆時年齢を共変量として用いる多変量解析法は、検診周期別に解析する横断的方法よりもより適切であると判断した。
少なくとも 4回の身長と体重の測定値のある 567人の対象者に限定した場合、DS86線量群に基づいた解析では、放射線被ばくに関連するきわめて有意な発育遅滞を認めた。この成長曲線モデルは欠測値を含む一連の多変量測定値にはまだ応用できないので、完全に身長と体重の測定値が利用可能な対象者に限定した。検診周期中に 3回の測定値を有する 254人の対象者を含めた場合の影響を調べるために、解析を追加したが、有意な発育遅滞は同様であった。254人の対象者については、各人ごとに身長と体重別の三つの測定値に単純な線形回帰モデルを当てはめて推察した期待値を欠測値のところに補った。市別、性別、DS86線量別および被爆時年齢別に検討した幾つかの比較の中で、最も大きな有意差は男女間のものであった。換言すると、身長では 12.5cm、体重では 約7kgの差が認められた。
広島・長崎間の測定値の差は有意に異なっていた。広島の対象者は長崎の対象者より平均して身長はおよそ 2.1cm高く、体重は 2.1kg重かった。原爆被ばくに起因した放射線関連発育遅滞は有意であった。市、性および被爆時年齢の影響を補正すると、DS86推定線量が 2Gy以上の被爆者の身長と体重は 0.01Gy未満の対象者よりも、身長は平均して 1.5cm低く、体重は 1.5kg軽かった(図3)。
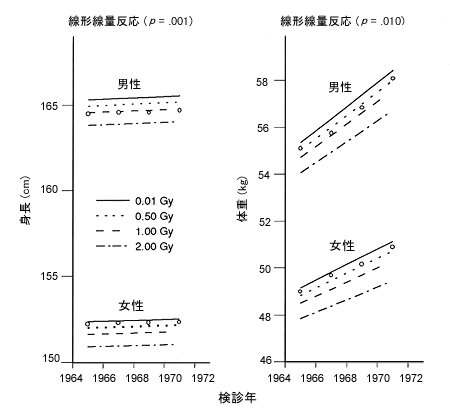
図3. 被爆時年齢0-9歳の対象者の身長と体重の観察値および期待値。
身長と体重の全体の観察平均値を丸で示した。
原爆放射線被ばくと発育成長パターンの変化との間には明確な関係があるようであるが、終戦直後の数年間の栄養不足や正常な家庭生活の崩壊などの他の要因が影響している可能性を評価することは困難である。1966年の心臓血管疾患に関する郵便調査結果の報告(ABCC業績報告書19-66)の中で、加藤らは、被爆者群間には職業もしくは教育レベルの違いによる差異はほとんど認められないが、非被爆者と被爆者の間には差があると報告している。住宅事情に関しては、1人当たりの居住面積は、広島・長崎いずれにおいても、被爆状況による有意差はなかった。本調査の対象者は、被爆者集団に限定した。
身長は主として遺伝的影響の結果であることから、対象者の予測成人身長を評価する上で、両親の体格は有効な共変量であるが、親の身長および体重の情報は入手されていなかった。1971年に J Belsky らが、被爆時年齢 0-9歳の子の親の世代に対応する年齢範囲である被爆時年齢 20-49歳の対象者について線量別の身長の差異は有意ではないと報告している (ABCC業績報告書 9-71)。
社会経済的要因の影響を調べるために、1963-1968年のAHS疫学調査質問票から得られた職業、教育歴、世帯主、および食習慣(和食、洋食、および中華の料理分類)などの共変量について成長曲線モデルによって評価した。身長と体重の多変量反復測定値と比較した結果、このような随伴変数間には有意な差は認められなかったが、放射線被ばくに関連した発育遅滞は明らかであった。成長曲線モデルに基づいた場合、栄養状態および社会経済状態の方が線量もしくは被爆時年齢よりもバックグラウンドの推定値により大きく影響するようである。したがって、栄養状態および社会経済状態などの随伴変数は、放射線被ばくに関係なく、調査対象者全員に均等に影響を及ぼしたと仮定した。また、遺伝的因子(すなわち、親の特徴)は無作為に選ばれた集団に等しく影響したと仮定するのは妥当であろう。