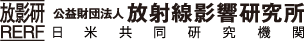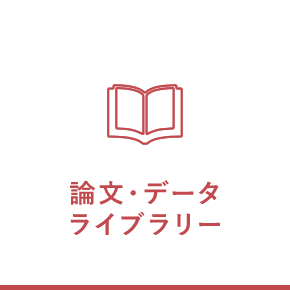寿命調査(LSS)における癌発生の追跡に腫瘍登録を活用
広島・長崎両市における腫瘍登録の発展と利用状況を説明し、LSS癌調査で果たしている重要な役割を強調する。
放影研疫学部・病理疫学部 馬淵清彦、病理疫学部(長崎) 早田みどり
この記事は RERF Update 2(2):5-6, 1990に掲載されたものの翻訳です。
癌のリスクを評価する場合、発生率データが死亡率データよりもはるかに有用であることはよく知られている。発生率では、患者は発病時に確認されるので、癌発生の時に基づく発生率のデータは、集団における発癌リスクの直接的な指標となり得る。これは癌の経時的発生パターンを調べる上で重要である。更に、乳癌や甲状腺癌などのように、予後が良好で死亡診断書には現れにくい腫瘍を調べる上でも、発生率調査は有効である。また、病院記録から詳細な医学データを直接入手することにより、正確かつ明確な診断のために必要な情報が得られる。死亡診断書に基づく調査ではこのような詳細な情報は得られないことが多い。
癌登録に向けての積極的なアプローチ
集団を基盤として各腫瘍例のデータを系統的に収集管理および解析するためには、腫瘍登録が必須である。30年以上前に広島・長崎において、両市の医師会の主導のもとに集団を基盤とした登録が設定された。当初から、ABCC-放影研が登録の日常業務を担当してきた。放影研職員は毎日地元の主要病院を訪問し、病院記録から必要な情報を採録している。癌登録のためのこのような「積極的な」アプローチは、米国の有名な腫瘍登録の多くで採用されているが、これによって広島・長崎の登録データの質が得られている。
データの質、ひいては、登録の信頼性を評価するためには、2つの数値が指標として用いられることが多い。すなわち、(i)組織学的に確認された診断を有する症例の割合(組織学的確認例、HV)および (ii)死亡診断書情報のみが利用可能な症例の割合(死亡診断書のみの例、DCO)である。現在、広島・長崎の登録におけるHVの割合は70%以上で、DCOの割合は 9%以下である。この成績は日本国内では屈指のものであり国際的に認められた腫瘍登録と並ぶ水準である(5大陸における癌発生、第5巻、国際癌研究機関、Lyon、France、1987年)。
放影研は組織登録にも支援を行っており、この事業では、広島・長崎で組織診断された腫瘍例が、良性・悪性ともに腫瘍組織スライドを添えて登録されている。この組織登録は、症例探知と診断確認のための補完的データ源となっている。最近、放影研が委託運営する県全体を対象とする癌登録が長崎で開始され、癌発生データのもう一つの情報源となった。
LSS集団全体の発生率データ:登録業務の標準化の所産
広島・長崎において精度の高い地域腫瘍登録を維持することは、放影研調査集団における癌発生について高精度のデータベースを確立するために必須である。腫瘍登録は、これまで幾つかの特定部位の癌発生の調査に用いられたことはあるが、長崎に関する 1959-1978年 LSS第9報(第3部)(若林ら、放影研TR 6-81)以来、LSSおよびその他の集団について、腫瘍登録を用いての発生率データ全体の解析は行われていない。その原因の一つは、広島でのデータ収集の遅れであった。しかし、ここ数年間に大きな改善がみられ、今日、LSS集団全体について最近の発生率データを求めることができるようになった。広島におけるデータ収集の問題は解決され、特定の主要病院の症例について情報が更新された。
これに加えて、LSS用の共通の腫瘍登録データベース確立の新しい試みが広島・長崎両市の登録担当者との協力により開始された。その目的は、両市の登録データの取り扱いを統一し、標準化することであった。両市の登録関係者の努力の結果、診断基準やデータ処理手順が標準化され、過去30年間に入手された癌患者 15,000例以上に関するすべての記録が再検討された。一貫性を確保するために、両市のスタッフは毎月会合を開き、コード化が困難な症例についても討議した。登録担当医師および病理学者の指導のもとにコード化について共通の規則を作成し、使用している。放影研研究情報センターの支援により開発された新しいデータベース・システムにデータを入力し、綿密な論理チェックを含む種々のデータ精度管理措置を実行している。
この発生率データを一見するだけで、このデータ・セットがいかに強力なものかをうかがい知ることができる。図は、LSS集団における 1958-1985年の癌発生例数と癌死亡数とを比較したものである。注目すべきは発生例数が合計ほぼ 10,000例に達していることで(被爆時に両市にいなかった人を除く)、この数値は合計約5,800例の死亡例数のほぼ 2倍である。乳房、甲状腺、皮膚、子宮(大部分が頚部)および尿路(大部分が膀胱)などの部位では、死亡例よりも発生例が極めて多い。消化器系の癌の症例数(約2,000例)も著しく多く、日本における胃・肝臓癌のバックグラウンド発生率が高いことを反映している。診断精度の向上とともに、症例数の増加がリスク評価にどのような影響を及ぼすかは、放射線発癌を研究しているすべての関係者にとって特に興味深い問題である。
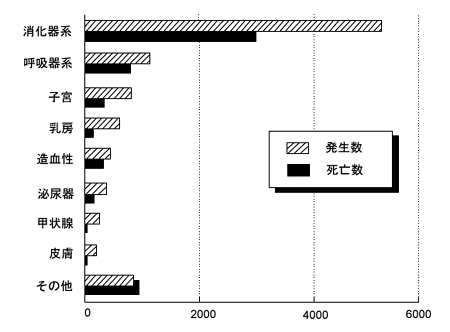
図. LSS集団における主要部位の癌発生数および死亡数、1958-1985年
転出は依然として問題
癌発生率データには多くの長所があるが、問題がないわけではない。主な問題の1つは、LSS対象者の多くが広島・長崎から長年の間に転出してしまったことである。生存中のLSS対象者のうち 約20%が腫瘍登録対象地域にもはや居住していない。転出率は、被爆時年齢と反比例している。転出者中に発生した癌は全国の死亡調査により確認されるが、広島・長崎の腫瘍登録の対象とはならない。住所データベース・プロジェクトが昨年開始され、各対象者の居住歴に関する情報を入手・維持するために積極的に実施されている。
当面は、以前の乳癌発生調査(徳永ら、放影研TR 15-84)と同様の方法を用いて、転出状況の補正を行った上で解析を行う予定である。転出は放射線量によって異ならないので、相対リスクの推定に、このような補正による偏りが生ずることはないと考えられる。LSS集団の発生率データ・セットの解析は現在統計部と共同で進めており、間もなく完了する予定である(編集者注:Radiation Research 137S:17-67, 1994を参照)。