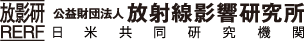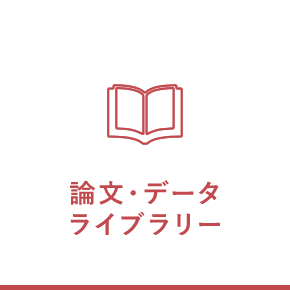1986年線量推定方式をめぐる中性子線量の不一致は、放射線リスク推定値に影響する
予想を上回る広島の中性子線量の裏付けにより提起されたやっかいな疑問
米国カリフォルニア大学付属 ローレンス・リバモア研究所 Tore Straume
この記事は RERF Update 4(4):3-4, 1992-93に掲載されたものの翻訳です。
1986年線量推定方式(DS86)は近年、放射線に起因するがんのリスク推定や、作業従事者および民間人の適切な放射線安全基準についての勧告作成のために、国際連合原子放射線影響科学委員会(UNSCEAR 1988)、米国学士院の電離放射線の生物学的影響に関する委員会(BEIR V)および国際放射線防護委員会(ICRP Publication 60)など影響力のある報告書で使われてきた。しかし、広島で採取した鉱物および鋼鉄中の中性子放射化測定値を、同じ試料についてDS86中性子のフルエンスとスペクトルを使って計算した放射化レベルと詳しく比較したところ、測定値と計算値の間に大きな相違があることが判明した(T Straume ら、Health Phys 63:421-6, 1992)。その違いは、広島の問題となっている爆心からの距離において、DS86推定値の 2-10倍くらいの中性子が実際にあったことを示した。これは人の放射線に起因するがんリスク推定に重要な意味をもつ発見である。
中性子放射化測定値
広島の最も問題となる爆心からの距離、1-2㎞について入手可能な放射化測定値は、中性子線量とはあまり関係ない熱中性子により産出される核種に今のところ限定されている。しかしながら試料から測定した熱中性子フルエンスはその爆心からの距離における大気中の高速中性子フルエンスに比例すると考えられており、そのため中性子線量にも比例することになる。これは試料を放射化した熱中性子のほとんどが、もとは高速中性子であり、それがその場の環境(すなわち土地と建物)の中で減速したためである。
原爆被爆者を対象とする線量推定にこの相違が及ぼす影響として考えられるのは、広島のDS86中性子線量を 1㎞で 2倍に、1.5㎞で 10倍にも増やさなければならないことである(この線量を仮にDS86+線量と呼ぶ)。
リスクへの影響
熱中性子放射化の測定値対計算値の割合に比例して中性子線量がDS86で過小評価されているならば(T Straumeら、上記引用文献)、1.5㎞における広島の中性子線量は現在考えられているより 10倍までの範囲で高いものとなるだろう。その結果、広島の放射線に起因するリスクに中性子が寄与する割合は、DS86で推定されているよりも大きくなる(一方でガンマ線の占める部分は少ない)。DS86の中性子が広島の放射線量に占める割合は数パーセントにも満たないが(「広島・長崎における日米合同原爆放射線推定再評価、DS86最終報告」WC Roesch編、1巻、1987)、それが放射線リスク推定に及ぼす影響はその高い生物効果比のため不相応に大きなものである。生物効果比は線量減少にともない増加する(RL Dobsonら、Radiaiationt Research 128:143-9, 1991)。
広島のデータから導かれたリスク推定値に対するこの中性子の不一致が及ぼしうる影響を示すため、広島の被爆者の血液リンパ球で測定した染色体異常を用いて、中性子からの放射線に起因するリスクの部分が推定されている(Preston ら、放影研業績報告書7-88、表4b)。広島に類似した中性子による染色体異常の線量反応曲線が利用可能であるので(Dobson ら、上記引用文献)、この種の推定にこの染色体異常を用いた方法は特にふさわしい代替法である(他の生物学的指標については、広島に類似した中性子に対して線量反応曲線が実験的に得られていない)。
広島の中性子にから起きた異常の部分(Fn)を計算するためにFn = Yn/Yt = anDn/Ytの関係を用いた。広島の中性子による異常頻度は広島原爆に類似した中性子に対する線量反応曲線(Dobsonら、1991)の傾き(an)と広島の被爆者の骨髄中性子線量(Dn)の積として推定されている(Dn値は放射線影響研究所の阿波章夫氏より提供)。広島の被爆者に対する異常総頻度(Yt)は、DS86の総骨髄線量(Dt、ガンマ線と中性子の両方)の関数として Preston ら(上記引用文献)が算出したものである。広島の異常データ(Yt)は「異常細胞の%」という形式で報告されているが、それと対照的に Dobson らのan値は「1グレイ当たり、細胞1個当たりの異常」という形で報告されている。上の式の分子に、分母と共通した単位を与えるため、 Ynを「細胞当たりの異常」から「異常細胞の%」へとを変換した。Dobson らの異常は細胞間でポアソン分布を示すと断定することによりこの変換は可能となった。
被爆後数十年を経た広島被爆者の血液リンパ球中の異常はすべて本質的に相互転座および含動原体逆位である(Prestonら、上記引用文献)。広島の原爆に類似した中性子に対しここで使われているan係数は二動原体および環状染色体について試験管内で得られたものだが、相互転座と含動原体逆位は二動原体および環状染色体と同じ頻度で誘発されていることが示されている(JN LucasらInternational Journal of Radiation Biology 61:830-5, 1992; LG LittlefieldらMedical Management of Radiation Accidents, CRC Press Inc, Boca Raton, Fla, USA, pp109-26, 1990)。また、全身被ばくした人々の血液リンパ球の相互転座頻度が被ばく後も経時的に完全に安定していることは相当数のデータにより判明している(T StraumeらHealth Physics 62:122-30, 1992; J LucasらCytogenetics and Cell Genetics 60:259-60, 1992; KE BucktonらMutagen-induced Chromosome Damage in Man, University Press, London, pp142-50, 1978)。したがって被ばく後最初の細胞分裂のとき試験管内で測定された広島の場合に類似した中性子の細胞遺伝的効果は、広島の被爆者の中性子により誘発された異常頻度の推定に用いることが可能である。
DS86が中性子線量を過小評価していると考えられている件については、「真の」中性子線量(Dn+)をDn+ = DnR の関係から推定した。ただしR は T Straume ら(Health Physics63:421-6, 1992)の適合曲線による中性子放射化の測定値対計算値の比率である。またこの場合、広島の中性子について推定した異常頻度(Yn+)はanとDn+の積である。広島の被爆者用の異常データとの適合性を持たせるため、この頻度を再び異常を持つ細胞の%へと変換した。広島の異常細胞の%、放射線量およびその他の関連パラメータは表に示した。
|
表. 広島の染色体異常データおよび他のパラメータ値 a
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a有効斜行距離の値は、上の表に示された骨髄線量をDS86空中カーマ値に対応させて、DS86の広島の放射線量対距離の関係(「日米合同線量再評価」WC Roesch編、1巻、1987年)から推定した。Ytの値はD Prestonら(放影研業績報告書7-88、表4b)による自然発生(すなわち0-0.005グレイの放射線を受けた集団)の異常細胞数を差引いた観察異常細胞の割合である。YnおよびYn+は、本文に記述した方法で推定した DS86とDS86+の中性子線量に対する異常細胞の割合である。骨髄の中性子線量(Dn)は阿波章夫氏(放射線影響研究所)より提供され、骨髄に対するガンマ線量(Dg)は放影研業績報告書7-88、表4b中の総線量から中性子線量を減じて得た。 R値は各距離における熱中性子放射化測定値対計算値の比である(T Straume らHealth Physics 63:421-6, 1992)。 |
| b予測値0.305%は観察値0.26%±1.68%より有意に大きいものではない。 |
中性子の不一致がリスクに及ぼす影響を 図 に示した。白い棒は広島のDS86中性子線量が真に正確で上方修正を必要としないという仮定に基づく。反対に黒い棒は広島のDS86中性子線量が低すぎるため、熱中性子の測定値対計算値の割合(T Straumeら、上記引用文献)に比例してすべてのエネルギーの中性子のDS86線量を増加させる必要があるという仮定に基づくものである。図によって、DS86中性子線量が正確であるならば、中性子は広島の放射線に起因する健康リスク全体のわずかの部分のみに影響したことがわかる。しかし、もし広島のDS86中性子線量が熱中性子放射化の量だけ過小評価されているとしたら(T Straume ら、上記引用文献)、広島の放射線に起因するリスクのほとんどは、現在考えられているガンマ線ではなく実際は中性子が原因となる。DS86による広島のガンマ線量はほぼ正確であるため(広島で測定されたガンマ線量とDS86で計算されたガンマ線量は比較的良好に一致したものだった)、ガンマ線のリスク寄与は 1,000mで 約50%、1,700mでは本質的に皆無であることが図から推測できる。また、距離が遠くなる(あるいは線量が減少する)につれて急激に増加する中性子からのリスク寄与は、広島のデータから得られた線量反応曲線の形に影響することになるだろう。すなわち、距離とともに増加する中性子線量成分は、低線量では、DS86により予測されるよりも曲線をさらに直線に近づける傾向があるようだ。
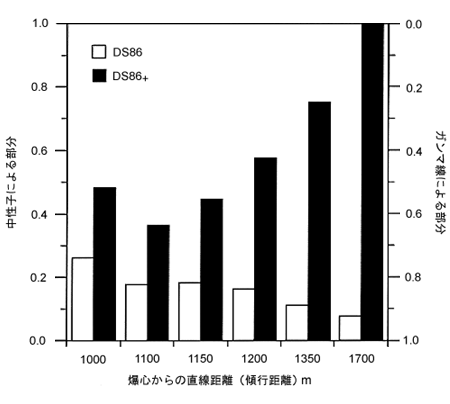
図. 広島の中性子に起因するリスクの部分。 DS86が正確である場合(DS86、白い棒)、およびDS86中性子線量を熱中性子放射化測定値に応じて増加させた場合(DS86+、黒い棒)。この線質別によるリスク推定値は広島の被爆者の染色体異常データ(Preston ら、放影研業績報告書7-88)と広島の原爆に類似した試験管内測定中性子の影響度(Dobson ら、Radiation Research 128:143-9, 1991)に基づく。ガンマ線によるリスクは右軸に示されており、中性子によるリスクを単に1から引いたものである。
謝辞
この調査は米国エネルギー省賛助の下、国防原子力庁(研究番号:92-281)の協力を得て米国ローレンス・リバモア研究所(契約番号:W-7405-Eng-48)が行ったものである。