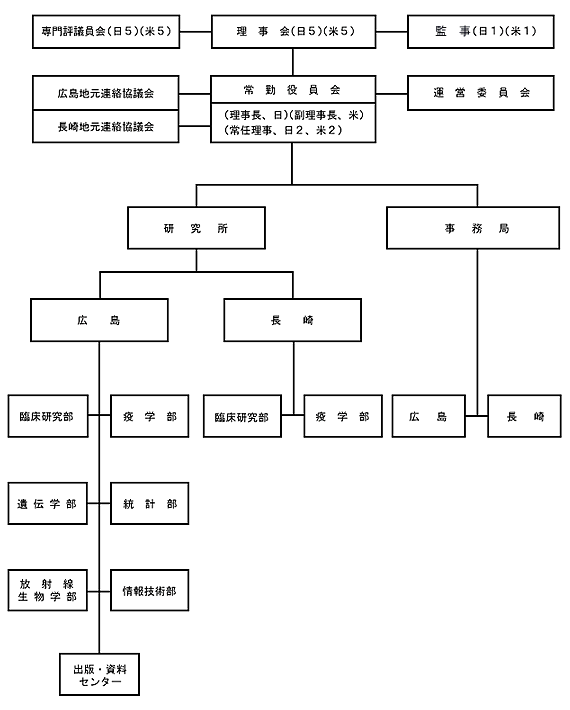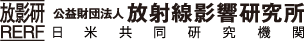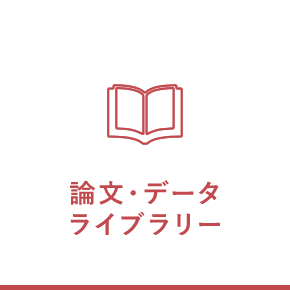放射線影響研究所の検討に関するブルーリボン委員会の報告書
Roger H. Clarke, 島尾忠男, H. Jack Geiger, 森 亘, Herbert L. Abrams, Dan Beninson, Valerie Beral, Keith H. Lokan, Albrecht Kellerer, Colin R. Muirhead(技術補佐)
解説・総説シリーズ 3-96
1. 前文
2. 概略
3. 調査集団
4. 学術的検討
(i) 疫学
(ii) 統計
(iii) 情報技術
(iv) 臨床研究
(v) 遺伝学
(vi) 放射線生物学
5. 将来計画
6. 総合計画および調査プログラムの管理
7. 国内および国際協力
8. 結論および勧告の要約
付録I. 委員名簿
付録II. 放影研の組織
1.1 1995年4月、放射線影響研究所(放影研)の専門評議委員会は、「放影研の調査研究活動がこれまで放影研のプログラムに関与したことのない外部の専門家グループにより慎重かつ徹底的に評価されることが妥当であり、望ましいと考える」という声明文を発表した。専門評議員会は、「放影研の現在および将来の調査研究活動の評価のため、著名な科学者から成る卓越した国際的委員会を組織する」ことを勧告した。米国エネルギー省および日本国厚生省は、国際ブルーリボン委員会を組織するという勧告を受理することに同意し、1995年10月11日、英国放射線防護庁Roger H. Clarke総裁を委員長に任命した。
1.2 委員会は、放射線研究および公衆衛生に関連する種々の学問分野を代表する科学者により構成された。医学、疫学、放射線生物学、免疫学、保健物理学、生物統計学、遺伝学、公衆衛生学において経験のある人物が委員に任命された。
1.3 厚生省とエネルギー省はそれぞれ4名の委員を指名した;厚生省は2名の日本人と日米以外の国籍を有する者2名を指名し、エネルギー省は2名の米国人と日米以外の国籍を有する者2名を指名した。委員会の最終構成は、付録Iに示すように、委員長1名、日本人2名、米国人2名、そして日米以外の国籍を有する者4名である。
1.4 委員会の任務は、放影研の将来の調査研究に関する勧告を作成するためにその活動を徹底的に検討することであり、特に以下の点に焦点を当てるように依頼された。
・現行調査研究プログラムの内容および質
更に以下の検討を行うように委員会に指導があった。
1.5 厚生省およびエネルギー省が最初に設定した日程では、1995年10月に委員の任命、1996年3/4月に広島・長崎で会議、1996年5/6月に委員会の予備結果を理事会で発表、1996年7月末までに厚生省、エネルギー省、および理事会に最終報告書を提出することになっていた。
1.6 実際は、1996年2月4-7日に広島放影研で、また7-8日に長崎で第一回の会議が行われた。会議の初日に委員会は、放影研の前身である原爆傷害調査委員会(ABCC)の初期の経緯について説明を受け、平和記念資料館を訪問した後、慰霊碑に花輪を供えた。
1.7 正式の会議の冒頭に放影研の重松理事長が歓迎の挨拶を行った。その後数日間にわたり疫学部、統計部、情報技術部、臨床研究部、遺伝学部および放射線生物学部の活動について各部の部長が報告を行った。各報告の後、非公式の会合が行われ、その中で各部の多数の研究員が参加して討議が行われ、委員会は科学的・医学的知見の深さを検討することができた。
1.8 委員会はまた、米国学士院の代表者とも会い、放影研の調査プログラムの審査および監督に関する説明を受けた。
1.9 委員会は藤田広島県知事と会見し、国際的な連結体制をもつ予定の広島国際癌センターに関する暫定計画について説明を受けた。
1.10 長崎での発表および討議は、疫学部と臨床研究部を中心に行われ、その後専門評議員会座長が同評議員会の見解を簡単に述べた。
1.11 1996年5月19-21日に英国放射線防護庁本部で第2回の会議が開催され、当報告書の内容に関して同意が得られた。1996年6月初旬に最終報告が完成した。
2.1 放影研調査プログラムは、様々な量の放射線に瞬間的に被曝した老若男女を含む大規模で明確に定義された集団に関する最も総合的な調査である。調査の展開につれて、幾つかの主要な分野に重点が置かれるようになってきた。主要な調査としては、原爆被爆者のがん死亡率および罹患率、ならびにがん以外の疾患による死亡率に関する疫学調査;被爆者集団の固定副次集団について継続されている臨床追跡調査による生物学的試料、経時的臨床測定値および罹病率のデータの収集;被爆者の子供の遺伝的および疫学的調査;被爆者から提供される他に類のない生物学的試料に対して最新の分子学的、細胞学的、生理学的、およびその他の技法を適用して放射線誘発変化の確認をし、これらの変化の背景にある生物学的機序の調査をすることが挙げられる。
2.2 原爆被爆者について得られたがん死亡率データは、がんリスク推定の主要な情報源となっている。他の調査から得られる情報は、現在では、原爆被爆者に基づく想定に取って代わるものとはならず、むしろそれを実証するものとなっている。国際放射線防護委員会の1990年勧告に示されたように、世界中の労働者および一般大衆の放射線防護基準は被爆者のリスク推定値に基づいている。事故による放射線漏れに起因する集団被曝および個人被曝に関するリスクも(例えば、因果関係に関する訴訟において)原爆被爆者データに基づき推定されている。放影研の調査により、胎児期の放射線被曝が身体的・精神的発達に影響を及ぼすことが示されており、胎内被爆者集団が高齢になるにつれ、この集団の過剰がんリスクの性質が明らかにされつつある。また放影研は、放射線被曝によるヒトの遺伝的影響の発生と性質に関する主要情報源でもある。
2.3 放影研の生物学的基礎研究は物理学的線量推定および疫学的方法によって以前は解決できなかった問題をすでに究明している。分子遺伝学において最近世界中で目覚ましい進歩が起こっているので、放影研は遺伝子座レベルで放射線の影響を究明する上で独自の中心的な役割を果たすことができよう。
2.4 放影研は、二度と生じることのないであろう比類なき集団を調査するユニークな調査機関である。現時点では、小児期および成人初期における放射線被曝の後影響について不完全な情報しか得られておらず、遺伝的影響の存在と性質について重要な所見が期待できる時期に差し掛かったばかりである。原爆被爆者を含む寿命調査(LSS)集団の追跡調査は、放影研疫学調査プログラムの中心である。追跡調査は、ほぼ完全な死亡確認を可能にする戸籍制度に基づく。1950-90年のLSS集団におけるがん死亡に関するLSS第12報は、放射線被曝に関連する過剰がんリスクが性別、被爆時年齢、到達年齢などの修飾因子にどのように依存するかに焦点を当てている。
2.5 放影研の遺伝調査プログラムは、ヒトにおける放射線被曝の遺伝影響に関する世界で唯一の調査である。遺伝調査の重要分野として、80,000人を越える被爆者の子供すなわち第一世代(F1)集団における死亡およびがん罹患の現在継続中の疫学追跡調査が挙げられる。この集団の43%は被曝した親から生まれ、残りは非被曝の親から生まれた子供である。この追跡調査は、死亡診断書に基づく死亡および腫瘍登録に基づくがん罹患の両方を基盤としている。疫学調査、先天性異常・死産・性染色体異常および相互転座に関する調査は、いずれの指標においても放射線被曝に関連した有意な増加を示していない。
2.6 放影研およびその前身である原爆傷害調査委員会(ABCC)により実施されてきた成人健康調査(AHS)は、世界で最も大規模かつ長期間実施されている臨床的集団調査の一つである。開始から40年間にわたり、AHS臨床調査プログラムは被爆者および地域社会のABCC/放影研への継続的支援を得るために、中心的な役割を果たしてきた。2年に一度のAHS検診は、被爆者との直接的な接触を可能にする放影研唯一の調査プログラムであり、放影研が行っている被爆者のための直接的な福祉活動ともなっている。また、LSS死亡追跡調査からも情報は入手可能ではあるが、がん以外の疾患への放射線の影響を理解するための主要情報源でもある。がんおよびがん以外の疾患に関する分子学的研究および他の生物学的指標についての調査を実施するためにも、AHSを通して収集される生物学的試料はますます有用性を増すであろう。ここでも、がん以外の疾患に関する放射線被曝の影響は依然としてほとんど未解明であることを強調したい。放影研臨床調査プログラムは、がん以外の疾患の罹患率を含め、放影研の疫学解析結果のすべてを生化学的・生理学的測定により実証するための貴重な情報源である。
3.1 1950年代から放影研は、広島・長崎の被爆者・非被爆者およびその子供を含む200,000人以上の健康を調査してきている。追跡調査の対象集団およびその追跡方法の概略を表3.1に示す。
|
表3.1 放影研集団
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
| *死亡について全対象者を定期的に追跡調査しており、広島・長崎県内ではがん罹患についても追跡調査している。加えて、喫煙、飲酒、食事などの生活様式の因子および出産歴に関する因子についての情報もLSS集団に関して1960年、1970年、1980年、1990年頃に行われた4回の郵便調査により収集している。 |
|
+成人健康調査副次集団の対象者は2年ごとに定期的に検査を受け、これらの対象者から大量の臨床データおよび生物学的試料が収集されてきた。 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| *DS86線量が推定されている人のみ。 |
結論
3.4 放影研の集団調査は、かくも多数の人が被爆したというだけではなく、各個人に関して記録されている情報の質が極めて高いという点でも他に例を見ない調査である。電離放射線の健康への影響をこのような詳細な形で調査できる機会が将来訪れるとは思えず、またそのような機会があったとしても、放影研に現存するだけの情報を収集するには更にもう50年を要するであろう。
概説
4.1 放射線影響研究所における学術的調査の「内容および質」を審査する際、同研究所の広範にわたる調査事業の重要性をどんなに高く評価してもしすぎることはない。その重要性は、調査している被爆者集団の独自性、ならびに放射線発癌調査を通じて提供される世界中の放射線防護基準のための基礎情報についての中心的役割にある。放影研は、再びこのような調査が実行可能とならないことが望まれるヒトへの放射線影響の調査といういまだ完了していない画期的な調査を行っている。放影研で行われている疫学・遺伝・臨床研究プログラム調査の多くは、必然的に体系的であり、その特性は変わらないことが必要とされている。
4.2 小児期の放射線被曝によるがん生涯寄与リスクは、被爆者集団の未解決な放射線防護問題のうち、最も重要な問題の一つであり、現在は不明確な仮説に基づいている。この問題解決には放影研の将来における観察が必要である。このような観察は、幼児期に被爆した被爆者ががん好発年齢に達するまでこれから数十年間引き続き行われなければならない。
4.3 かつては放射線誘発がんのリスク推定は、主として放影研のがん死亡率データとその解析に基づいていた。がん罹患率に関する最近の広範にわたる調査により、リスクモデルの作成とリスク因子導出のためのもう一つの同様に重要となる基盤が加わった。
4.4 広島での学術的プログラムは、疫学、統計、情報技術、臨床研究、遺伝、放射線生物の6分野について検討した。長崎で行われている疫学調査および臨床調査プログラムについては広島の当該調査プログラムと一緒に検討した。
4.5 広島・長崎の疫学部の主要任務は以下の通りである。
・ 寿命調査(LSS)、胎内被爆者、F1(被爆者の子供)集団についての死亡とがん登録に基づく追跡調査
・ 広島・長崎の腫瘍・組織登録の維持
・ 放射線被曝と他の生活様式因子の病因学的関連の徹底的調査
4.6 全体的には、疫学部は約200,000人の追跡調査を担当している。追跡されている最大のグループは寿命調査(LSS)集団である。現在まで、DS86線量が算出されている調査対象者において約8,000例のがんが発生しており、約20,000件の組織試料が外科手術および剖検により収集されている。LSS集団のほとんどの対象者について生活様式情報が約10年間隔で1960年、1970年、1980年、1990年頃に行われた4回の郵便調査によって収集されている。
4.7 疫学部は、統計部と緊密に協力し、LSS集団における死亡と放射線被曝との関係について定期的な報告を行っている。死亡データの蓄積に伴い、その報告書は、放射線影響の検証に関する比較的直接的な記述から、がんまたはその他の原因による死亡のリスクに影響を及ぼす因子についての詳細な解析・説明へと変化してきた。最新の報告書(LSS第12報)は1950年から1990年までの癌死亡を扱っている。少なくとも100件の死亡が認められた12の部位の固形がんについて単位線量当たりの過剰相対リスクが推定されている。これらのがん部位の大部分には、放射線被曝に関連した統計的に有意なリスクの過剰が認められる。更に、多くの固形がん部位についてのデータは、共通の過剰相対リスクと一致している。
4.8 全固形がんの死亡データでは、0-3 Svの範囲で顕著な線形線量反応が認められるが、白血病の場合、線量に伴うリスクの傾向は、上向きの非線形曲線を示す。過剰白血病リスクは被爆後15年間が最も高かったが、固形がんの絶対過剰率は、年齢の増加に伴うバックグラウンド率の増加とほぼ比例して、追跡期間を通して増加してきた。過剰相対リスクは、成人期に被爆した人よりも幼少期に被爆した人の方が高い傾向にあり、ほとんどの性別に関係しないがんについては男性よりも女性の方が高い。しかし、年齢別過剰絶対リスクは全般的に性別または被爆時年齢にほとんど依存しない。
4.9 原爆被爆者のための初期のがん罹患監視プログラムは、1940年代後半に開始された白血病およびその他の血液疾患登録作業から派生したものである。地元医師会の協力を得て、集団を基盤とした腫瘍登録が1957年に広島で、1958年に長崎で開始された。これらの登録は当初からABCC-放影研により運営されており、日本で最高の腫瘍登録と一般に見なされている。1987年までのLSS集団におけるがん罹患データは、1994年に発表された包括的報告書の基盤となった。これらのデータはがん死亡データを補足する上で重要である。固形がん罹患の追跡期間は死亡の追跡期間よりも短いにもかかわらず、がん症例数は死亡例数より多い。更に、罹患データは致死率の比較的低い乳がん、甲状腺がん、皮膚がんなどについてリスク推定値を提供し、死亡診断書が不完全または不正確なことが多いがん(例えば肝臓がん)の調査に役立つ。LSSにおけるがん罹患についての調査は、一連の詳細な部位別研究により続行されている。
4.10 これまでのLSS追跡調査により、がん以外の疾患による死亡と放射線量との間に関連性があることが示唆された。この問題については成人健康調査の一環として調査が行われてきた(4(iv)参照)。更に、拡大死亡追跡調査に基づく報告書が現在作成されつつある。胎内被爆者の追跡調査では、合計症例数は少ないが、放射線関連の死亡率の増加が示唆されている。対照的に、F1集団においては線量に伴う死亡率またはがん罹患率の統計的に有意な傾向は認められていない。これらの調査を続行するほか、LSS集団におけるがんの家族集積性についての調査も計画中である。 4.11 疫学部が追跡している集団は世界でも最大かつ最も良く記録された集団の一つである。この集団では、たとえ電離放射線被曝がなかったとしても、長期間にわたり収集された生活様式および健康に関する情報の価値は他に類を見ることができない。疫学調査プログラムは、放影研調査の中核となるものである。日本の生活様式の健康への影響(特に食事因子)および過去50年間にわたる生活様式の変化の影響について多大な関心が示されている。放影研に既に存在する学術データを完全に利用するには、疫学調査を更に強化することが必要であろう。国内および海外の疫学者との共同研究、特に放射線被曝に直接結び付かないデータのいくつかの側面について探求するような共同研究をすることが、関係者全員の利益となるであろう。
結論
4.12 疫学部が保有するデータは、放射線の健康への影響を評価するためだけではなく、様々な生活様式因子がもつ健康への影響および同因子と放射線被曝との相互関係を決定するために大変重要である。現在、データを解析し、発表するための努力は不十分であり、これまでに収集され将来的に価値のある情報が十分に活用されていない。
勧告1
疫学部は死亡およびがん罹患に関するデータを引き続き収集すべきであり、この作業は強化されるべきであると勧告する。データの量と範囲からみて、放影研の管理者はこれらの調査を最優先すべきである。更に、既に収集済みの将来的に価値があると思われる情報を解析するために国内、海外の他の研究所の疫学者と共同して調査を遂行するべきである。
4.13 疫学部および統計部は緊密に連結し、共に放影研の中心を成している。両部の任務は、原爆被爆者の追跡調査の継続と他の調査プログラムにとって必要不可欠なものである。
4.14 被爆者における最新のがん調査により、いわゆる絶対リスクモデルと相対リスクモデルの中間的存在である修正リスクモデルを支持する情報を得た。当該作業の継続と、必要性が増してきている死亡率と罹患率データ解析の連結には、疫学分野での更なる努力に加え、統計部門における巾の広い、安定した研究者チームが必要である。
4.15 原爆被爆者に関する広範囲な調査を通して、放影研統計部は、世界で行われている他の放射線調査に多大な影響を持つようになった。最近、同部は旧ソビエト連邦南ウラル地方のマヤークで高線量に被曝した核施設従業員およびテチャ川汚染地域の集団について研究している放射線疫学者と積極的な共同研究を開始した。これら二つの調査は継続的放射線被曝による健康影響を扱うものであるが、短時間に放射線被曝した原爆被爆者を調査する上で大変重要な補完的役割を将来担うようになるであろう。この新しい調査は、主として原爆被爆者について行われた作業を模範にして行われるので、これにより放影研の調査プログラムに対し、重要な情報のフィードバックが得られ、その重要性を増すことになるが、その一方で負担も増加することになる。
4.16 同部職員は共同研究者と共に、現在疫学データ解析用に世界中で使用されているEPICUREというソフトウェアを開発した。本ソフトウェアは様々な調査の比較可能性を高めることができるので引き続き開発していくことは重要である。
4.17 がん死亡率および罹患率の調査結果は多数の文献に報告されてきたが、今では初期の方針と大きく変わって、ここ何年にもわたり、よく記録された基礎データセットを放影研以外の研究グループが解析に使用できるようになっている。しかし、胎児期の被曝による奇形、特に精神遅滞およびIQの低下に関する重要な観察の調査結果については、同様な成果はまだ得られていない。重要な解析は行われているが、統計処理が系統的ではなく、雑誌発表も十分ではない。胎内被爆者の知能テストまたは他の調査結果のような基礎データセットは、放影研以外で利用可能にはなっていない。
結論
4.18 優れた調査が統計部で行われており、研究所全体の大きな活力源となっている。同部の貢献は、蓄積されたデータセットを世界レベルのヒト放射線リスク推定の基盤とするためには必要不可欠のものである。
勧告2
統計部は疫学部と協力して放射線被曝リスクの解析を引き続き行うこと、また統計部門における質の高い調査研究を維持すべきことを勧告する。
勧告3
統計部は、引き続き他の研究グループが死亡率および罹患率に関する基礎データセットを解析に使用できるようにすることを勧告する。同様に、精神遅滞、IQ、その他胎内被曝に関連した調査結果などに関するデータセットも利用できるようにしていくべきである。
4.19 委員会は、情報技術部の有益な発表を聞き、放影研の歴史上ほとんどの期間、各調査研究プログラム関連のデータは一連の大型汎用コンピュータ上で維持され、多くの場合、研究所内で開発せざるをえなかった特殊なソフトウェアを用いて解析されていたことを学んだ。
4.20 PCおよびRISCをベースにしたワークステーションの性能が向上し、価格が下がったこと、またコンピュータ通信、データベース管理、データ解析、グラフィック処理などのための汎用ソフトウェアも利用可能になったことで1980年代後期までに大型汎用コンピュータから分散型ネットワークへの移行が考えられるようになった。そこでネットワークに接続したIBM互換PCとUnixワークステーションを使う統合システムを設置する主要な作業が1991年に開始され、1994年度末に大型汎用コンピュータは撤去された。
4.21 この方向転換により放影研は大きな利益を得た。長崎・広島間の通信を含む放影研内の通信は向上し、インターネットとそれに付随する施設へのアクセスが可能である。また、現在放影研では利用が容易なビジネス管理用の市販ソフトウェアを使用することができる。更に、個々のPCにより特定のプロジェクトの統計解析、データ処理およびグラフィック処理の多くを独立体制で処理することができる。
4.22 実際、分散型ネットワークへの移行はかなりの経費節減を可能にした。全般的に前システムよりも強力な現システムは、設置、維持ともに前システムよりも費用がかからない。
4.23 恐らく、この新制度の最も重要な点は、Unix環境にリレーショナルデータベースを設置し、基本名簿、腫瘍登録、組織登録、LSSおよびDS86線量推定などの主要データファイルを同データベースに移したことである。多くの冗長データを除去したことに加え、重複している調査プログラムのデータを統合することにより、解析および調査に利用可能な対象者個人情報の作業ファイルの検索が大いに簡素化される。
4.24 個人に関する関連データ全てが効率的に整理できるように、現在依然として独立したファイルに保存されているデータをさらにデータベースに組み込んでいく作業がまだ多く残されており、統合を一層進める作業が予定されていると理解する。同時に、単一の統一データベースシステムの中での操作を可能にすることは有益であり、その際系統的な方法でデータが含まれるようにするために、種々のデータソースを慎重かつ綿密に調べることが必要である。つまるところ、放影研の全主要データを一つのシステムにまとめることにより、集団調査一般に用いるためにより充実した強固なデータを維持できるようになる。
4.25 今後に得られる研究結果の観点からいうと、コンピュータ環境の変更は調査の水準を高め、これからどのような方向性が取られても効率的に従うことができる方法を切り開いていくものと委員会は考える。
4.26 情報技術部は、委員会への発表の際、放影研の調査の支援においてまだ終えていない作業がたくさん残っていることを認めており、同部の将来計画の方向性を明確に把握しているようである。また、同部の職員は、新しくなじみのないシステムを導入する際、同部のユーザーサポートの質を向上させ、ユーザーが問題に遭遇した場合トレーニングを行い援助しなければならないという点を指摘した。
結論
4.27 効率の良いデータ管理およびコンピュータ処理は、放影研の調査の成功の基幹となるものである。委員会は、放影研がコンピュータ基礎構造について正しい方針決定を下し、同部は優秀な技能および英知をもってその決定実行に取組んできたと考える。中央連結型データベースの構築において過去数年間見られている進歩には目を見張るものがある。
勧告4
数十年にわたり収集された大量のデータが正しく保存、記録され、放影研の研究員がアクセスできるようにすることは大変重要であるので、情報技術部に引き続きゆるぎない支援を与えることを勧告する。
4.28 臨床研究分野の調査プログラムは、120,000人の寿命調査(LSS)集団から選ばれた約20,000人から成る成人健康調査(AHS)集団に基づいて実施される場合が多い。1978年以来、寿命調査対象者約2400人および胎内被爆者約1000人がこの集団に追加された。すべてのAHS受診者は、病歴調査、理学検査、心電図、胸部X線検査、超音波検査、血液検査などを含む、詳細な検診を2年に1度受ける。生活様式についての情報ならびに骨密度測定や婦人科検査を含む特別検査の結果などのその他のデータも収集される。
4.29 委員会へ提供された情報から、本調査プロジェクトの多くが必然的に繰り返し実施される性格のものであることは明瞭であった。現在の調査プロジェクトの多くは過去の調査プロジェクトと酷似しており、その幾つかは、基本的には以前の所見に記録を加えるというものである。しかし、この種の組織化された、繰り返し実施される系統的かつ詳細な調査および臨床的追跡調査は、がんリスク推定およびがん以外の疾患と放射線被曝との関連性の究明の基盤となる正確なデータベースの確立という目標の達成にとって不可欠である。寿命調査と同様、成人健康調査は、他に類を見ない価値を持つ被爆者集団にその重要性の基盤を置いている。
4.30 臨床研究分野における調査プログラムの重要な機能は、広島・長崎の被爆者集団と放射線影響研究所およびその調査プログラムを結び付けることである。AHSは放影研と被爆者とを結ぶ、事実上唯一のきずなである。AHSは被爆者に目に見えるサービスを提供しており、高い受診率が示す通り、被爆者はこれを有用と見なしている。AHS集団の2年に1度の検診は、医療福祉事業の要素 -支援、看護、配慮など- も備えており、これがなければ両市における被爆者集団の全面的な協力が得られたかどうかは疑問である。AHSは、被爆者の健康管理に直接有益な効果をもたらす重要な調査プログラムの一つと見なすべきである。
4.31 AHSの寄与はおおむね次の三つに分けられる。
- がんならびに疾患発生における寄与因子または交絡因子に関する臨床データおよび実験室データを提供することにより、寿命調査の所見を増加、充実し、あるいは補完する。
- 寿命調査の中心的課題以外の問題、特に死亡率またはがん罹患率データでは調査できない放射線の影響の探知および解析を行う。
- 放影研の他の調査に不可欠な生物学的試料を提供する。
4.33 胎内被爆者における有意な放射線関連の影響としては、小頭症や精神障害が挙げられる。更に、胎内週齢8週から15週の間に胎内被爆し、後年重度精神遅滞と診断された人に脳の障害が認められた。また、子宮筋腫罹患率ならびに副甲状腺腺腫罹患率の有意な線量関連の増加が被爆者に認められた。放射線との関連が良く知られている水晶体混濁は、20年前に実施されたこの集団の調査でその罹患率の増加が認められた。水晶体混濁について最新の調査が計画されている。被爆者集団の高齢化にかんがみ、より高度な白内障調査を実施することが望ましくかつ急務である。
4.34 心臓血管疾患罹患率、特に心筋梗塞および脳梗塞の罹患率ならびに大動脈弓石灰化および収縮期高血圧の有病率には放射線関連の増加が示唆されているが、放射線被曝とアテローム性動脈硬化症の間に真の関連性が存在するか否かは今後の調査を待たなければならない。同様に、被爆者集団における甲状腺腺腫および慢性肝疾患の罹患率の増加がAHS調査で示唆されているが、慢性肝疾患については高レベルの肝炎ウィルス感染を反映するものかもしれない。別の調査では、放射線に被曝しなかった人と比べて高線量被爆者に早期閉経が認められた。閉経前の女性における血清FSHおよびエストロゲン値の解析が進行中である。
4.35 F1集団については、1歳以降には系統的な臨床調査は行われていないが、先天異常の死亡率または罹患率の増加は認められない。優性遺伝疾患および多因子性遺伝疾患は10歳以後に発現することが多く、後者の場合は通常成人期以後である。この集団について更に調査を行う必要がある。これは遺伝学部の担当であるが、臨床調査プログラムの直接的関与が必要である。胸椎骨折の調査では放射線被曝との関係は認められない。老人性痴呆の調査が進行中であり、また8000人以上のAHS対象者に対して、加齢に伴う死亡または罹病の予測因子としての生理学的測定値の評価が行われている。加齢の促進は認められない。
4.36 臨床調査プログラムでは、過去30年間の調査活動の結果、110,000件の凍結血清試料ならびに11,000件の血漿試料が維持されている。更に、放射線生物学部は13,000件のリンパ球試料を液体窒素中に保存している。これらおよびその他の試料により、交絡因子のそ及的決定や、免疫システムの特別調査が可能である。更に、臨床調査プログラムでは、両親と子供のトリオからDNA試料を得るための主要プロジェクトのため、800家族(1600人の親と1200人の子供)から細胞株を入手した。これは、ヒト生殖細胞突然変異に対する放射線の影響探知のための世界で最大の固定集団である。最後に、臨床調査プログラムは、電子スピン共鳴法を用いた歯のエナメル質の線量測定に必要な歯の提供呼びかけにも関与している。
結論
4.37 本調査プロジェクトの重要性は、LSSおよびAHS集団の追跡調査の規模と質、LSSおよびAHSと関連して行われている疫学および統計学調査の質ならびに胎内被爆者の継続的評価に反映されている。臨床研究部の役割は全ての部門の多くの目標の達成に不可欠である。
4.38 本調査プロジェクトの内容と質は、臨床研究部が他のすべての部門に対して行っている次のような協力に反映されている。
- 致死性および非致死性がんならびに放射線被曝のがん以外の疾患に及ぼす影響についての臨床データの提供
- LSS集団に認められた種々の関連性についての詳細な調査
- 他に類を見ない、血清、血漿およびリンパ球試料の提供
- 被爆者への重要な「掛け橋」的役割
勧告5
臨床調査プロジェクトの多くは今後も続行すべきであるが、調査プログラムを厳密に検討し、成果が得られないと思われるものは中止することを勧告する。1945年には子供で、現在成人に達している人については、放射線感受性が若年被爆者で最も高いと思われるので、調査を継続すべきである。
勧告6
AHSは被爆者の福祉のために極めて重要であり、放影研に対する被爆者の非常な協力を可能にしたと考えられるので、この観点から重要なサービスの継続を勧告する。被爆者の高齢化が進んで、健康問題は更に複雑となっており、高い受診率を維持するための配慮が必要である。(v) 遺伝学
4.39 遺伝学部は主に二つの課題に取り組んでいる。第一の、従来からの課題は原爆被爆者の子供における遺伝的障害の評価である。第二の課題は、線量再構築とDS86線量体系の妥当性の検証を目的とした、細胞遺伝学的調査ならびに最近開始されたその他の生物学的線量評価である。
被爆者の子供
4.40 原爆被爆者の子供(F1)における妊娠終結異常、がん以外の疾患による死亡率、20歳までの悪性腫瘍、細胞遺伝学的異常および遺伝生化学的蛋白質異常について広範な調査が行われたが、過剰は認められなかった。これにより、当初上記の影響に対するヒトの感受性は初期の研究で観察されたマウスの感受性よりもかなり低いという結論に至った。最近、マウスデータについて厳密な再評価がなされた結果、電離放射線の突然変異誘発性影響に対してヒトがマウスよりもはるかに低い感受性を示すかどうかは現在のところ不明である。
4.41 動物データについての判断が確定していないことから、放射線誘発の遺伝的障害のリスク推定値を動物研究に基づいて決定して良いかどうか不明である。このような理由および他の理由から、原爆被爆者の家族についての調査から得られた所見は最大限生かされるべきである。遺伝学部の最近の調査では、被爆した両親のいる500家族と、これと同数の被爆者のいない対照家族との間に突然変異率の差があるかどうかを見るため、Bリンパ球永久細胞株を用いた分子生物学的研究に重点が置かれている。最新の技法(例えばミニサテライト遺伝子座における突然変異の検出法)が試験的に導入されて研究が行われたが、現在までのところ、被曝ゲノムに突然変異率の増加は認められなかった。このような研究はすべて急速に進歩しつつある分子生物学的技法に基づいており、従って初期的活動と見なすべきである。分子生物学における今後の進歩により、更に完全な解析が可能になり、最終的には上記家族のゲノムにおける分子学的変化の精確な評価が可能になるであろう。
被爆者集団
4.42 細胞遺伝学調査は、長い間放影研とその前身機関の活動の重要な部分を占めてきた。初期には、この調査活動は二動原体などの非対称性染色体異常の決定に限定された。この異常は「不安定」であり、細胞増殖に伴って消滅するので、短期間、通常は数年間しか存在しない。広島と長崎との線量依存性の差など、重要な問題が依然として未解決であるが、上記の理由のため、この調査は最近余り重要視されなくなった。
4.43 分子生物学の進歩がこのような状況を変え、FISH(fluorescence in situ hybridization、蛍光in situハイブリダイゼーション)の技法を通じて、染色体を用いた生物学的線量測定に新機軸をもたらした。FISH法により、今では多くの人員に頼ることなく、対称性、すなわち安定型の染色体異常を探知できるようになった。遺伝学部は、何年も前の放射線被曝についてそ及的生物学的線量測定を可能にするFISH法の開発と実際の利用を率先して行った。
4.44 遺伝学部はまた、マヤークおよびテチャ川流域で調査しているロシア人研究者に対してFISH法導入の指導を行った。ヨーロッパの研究者もこれに関与したことから、細胞遺伝学的方法の相互比較および改善のための国際的な協力ネットワークが成立した。FISH法には依然として種々の未解決の問題があるので、現在の相互比較ならびに新しい方法の種々の被曝集団への適用を継続し、更には拡大することが重要である。FISH法適用の対象となる集団としては、原爆被爆者、マヤークの核施設作業従事者、テチャ川流域集団、セミパラチンスク核実験による降下物に被曝した集団ならびにチェルノブイリ事故により被曝した特定の集団などが挙げられる。
4.45 遺伝学部は、ESR(electron spin resonance、電子スピン共鳴法)による線量測定法を改良し、歯の線量測定に応用した。ESRによる線量測定は細胞遺伝学的調査を補完するものであり、従って同様に高い優先順位が与えられるべきである。最高の技法を使用すべきではあるが、遺伝学部が単独で方法論的作業を行う必要性はないので、同部が新しい技術、特に歯のエナメル質に加えて象牙質を用いる方法を共有するために外部の研究所との連携を確立したことは適切である。
4.46 FISH線量測定法とESR線量測定法という二つの技法を原爆被爆者およびその他の被曝群に並行して適用することにより、染色体研究は結果の相互比較から多くを得ることが示された。歯を用いた線量測定法は少数の症例に限定して行われるが、低線量測定に適用可能と思われ、測定値の変動は少ない。従って、染色体研究結果の精度を高めるための較正法として使用し得る。
結論
4.47 分子生物学的研究は最も詳細な測定を可能にし、将来の研究の焦点となるであろうが、被爆者の子供(F1)の健康については従来の調査を継続し、更には拡大することが必要である。また、分子学的研究が放射線による多因子性遺伝障害の問題の解決に近づくのはどの時点であるのか明瞭ではないので、従来の調査は今後も重要である。
4.48 被爆位置における、現在改善されつつある物理学的線量測定および個人データと染色体データ、歯のデータならびに建築材料、陶磁器、宝石といったその他の資料についての固体線量測定データとをより密接に関連付けることができるようになった。従来、線量測定は放影研の活動ではないが、新しく認めれたこのような関連性はDS86線量体系の検証に極めて重要である。
勧告7
被爆者の子供(F1)の健康に関する調査は、多因子性疾患についてのデータを提供するかもしれないし、また被爆者とその子供に直接恩恵を与えると考 えられるので、今後も継続するよう勧告する。
生物試料に基づく線量推定値と物理学的線量推定値との比較に必要なFISH分析およびESRのための生物試料の保存、ならびにこれら試料についての記録作成を勧告する。
勧告9
将来の分子遺伝学研究のための生物試料の保存、ならびに保存試料についての記録作成の続行を勧告する。
勧告10
細胞遺伝学における最も進んだ方法および専門知識・技術を今後も放影研に導入することを勧告する。
4.49 放射線生物学部は放影研では比較的新しい研究部門である。この部門の設立目的は、放影研の有するまれな生物試料を十分に利用し、特に原爆被爆者、その子供および孫における家族関係についての分子生物学的研究を実施する可能性を探ることであった。分子腫瘍学、免疫学および体細胞突然変異についての研究が進行中である。体細胞突然変異研究は、生物学的線量測定を実施している細胞遺伝学グループの活動とある程度関連している。分子腫瘍学研究と免疫学研究は密接に関連しているが、これは発がんの分子学的および細胞学的過程の解明を主に目的としているためである。
分子腫瘍学
4.50 放射線生物学および放射線研究一般における最も顕著な進歩は分子疫学と呼ばれる分野の出現である。電離放射線のような腫瘍発生の原因となる因子に特異的な - あるいはそれと相関関係にある - 分子マーカー、すなわち遺伝子変化があるかどうかは依然として不明である。この点の究明を目的とした分子生物学研究が世界中の多くの研究所で現在実施されている。特定のマーカーが探知されれば、放射線疫学は全く新しい基盤を持つことになる。これが放影研の中心的調査プログラムにとって重要であることは明瞭であろう。このような経緯にかんがみ、原爆被爆者から得られ、保存されている腫瘍および正常組織試料は極めて重要であり、保存試料の拡大と維持は放影研の主要な任務である。また、適切な計画立案および利用可能なあらゆる方法に関する専門的知識に精通している必要がある。放射線生物学調査プログラムはこの目標を見事に達成している。このプログラムでは40年以上前の剖検試料を利用する方法を検討し、実際、遺伝子増幅法が新鮮な試料と同様この保存試料にも利用できることを示したことは特に重要である。種々の既知のがん遺伝子および腫瘍抑制遺伝子について研究が行われ、この研究グループの優秀性を証明している。
免疫学
4.51 リンパ系の機能について熟知することは、発がん機構解明のための前提条件である。重要な問題は依然として未解決であり、従って放影研がその保有する豊富な情報を用いて求められている研究に寄与するのは妥当なことである。放影研における調査の特徴は、加齢の影響ならびにT細胞の免疫能への加齢と放射線被曝の同時効果を調べるのに十分な長さの期間にわたって、原爆被爆者についての調査が繰り返し実施されているということである。各正常細胞および幹細胞のクローン性拡大については依然としてほとんど知られていない。従って、クローン性拡大についての放影研での最近の研究は特に興味深い。このような研究によれば、極めて多くのT細胞、B細胞、赤血球前駆細胞および骨髄前駆細胞に同一の染色体異常が現れることがわかっている。このような研究は、造血システムの動態についての、より正確な定量的知識の得難い基盤となり、放影研においてしか観察できない資料を用いた重要な国際協力の中心的役割を果たし得る。
体細胞突然変異
4.52 HLA、TCRおよびHPRTという三つの異なる遺伝子座における体細胞突然変異の測定が、生物学的線量測定の代替方法として使用できるかどうか検討されている。このような測定系は放射線被曝が最近であれば使用できるが、これらの体細胞突然変異は、数年あるいはそれよりはるか以前に生じた放射線被曝についての信頼できる情報を提供できる程持続的ではない。原爆被爆者についての幾つかの調査によって、赤血球グリコフォリンA(GPA)突然変異の測定が、過去の放射線被曝についての調査に用いる方法として有力であることが示唆された。しかし、全体として、リンパ球についてはFISH法が、また特に歯についてはESRが生物学的線量測定法として優れているようである。この分野における進歩の可能性はあるものの、動向は不明瞭なので、体細胞突然変異の研究の妥当性については明言できないが、現時点では特に高い優先順位を与えるべき研究とは思われない。
結論
4.53 分子生物学の進歩にかんがみ、原爆被爆者から得られ、保存されている腫瘍試料および正常組織試料は極めて重要であり、保存試料の拡大と維持は放影研の主要な任務である。
4.54 放影研における免疫学研究の特徴は、加齢の影響ならびにT細胞の免疫能への加齢と放射線被曝の同時効果を調べるのに十分な長さの期間にわたって原爆被爆者についての調査が繰り返し実施されているということである。クローン性拡大に関する最近の研究は特に興味深い。
4.55 体細胞突然変異測定系は放射線被曝が最近であれば使用できるが、体細胞突然変異は、はるか以前に生じた放射線被曝についての信頼できる情報を提供できる程持続的ではない。
4.56 疫学調査における因果関係の確立には、強力な関連性の他に幾つかの条件が必要である。なかでも、「もっともらしい機序」を仮定することが重要である。メカニスティックモデルにより行うこの仮定は、観察を超えた外挿、特に低線量被曝の場合の外挿の基盤ともなる。
4.57 従って、放影研における放射線リスクの調査は、明示的にも暗示的にも、常に機序とモデルに関連して行われることは明瞭である。分子遺伝学に基づく発がん過程についての知識の飛躍的な増大は、モデルがこの方向に進むことを示唆している。放影研にモデルについての専門家を配置することは妥当でないと思われるが、実験研究から得られたデータが放影研の研究戦略に影響を与えると思われるので、その意味を常に考慮することが極めて重要である。
勧告11
放射線生物学部は分子疫学と免疫学に重点を置き、発がん過程のモデル作成に関与している世界中の研究グループと放影研とが強力に連携することを勧告する。
5.1 LSS第12報は、特に小児期に被爆した人について、現在国際的に推奨されている放射線誘発がんリスク推定値に関する不確実性はいかなるものかに焦点を当てる。今日までに得られた調査結果は、固形がんの過剰リスクは存続し、過剰率は生涯を通して増加することを示唆している。成人期に被爆した人の固形がんの過剰相対リスクは、生涯を通してほぼ一定である。小児期に被爆した集団では、相対リスクが少し減少していることを示す証拠がある。しかし、この集団の過剰率(すなわち絶対リスク)は、成人期に被爆した集団に観察されるリスク増加と同様に年齢の増加に従い増加している。小児期に被爆した集団では、がんの合計死亡数は現在のところ少ない。しかし、その数は5年ごとに倍増しており、過剰症例数の推定値もほぼ同じ割合で増加している。
5.2 50歳以上で被爆した集団の生涯追跡調査はほぼ完了したが、LSS集団の半数以上、また小児期に被爆した集団の90%以上がまだ生存している。表5.1はこの集団の実際および推定の人数を示す。西暦2000年までには20歳未満で被爆した集団のがん死亡が、1990年までに観察された例数の3-4倍になり、21世紀初頭の10-15年間は急速に増加し続けるであろう。従って、小児期または若年で被爆した集団の追跡調査の継続が、この集団の放射線誘発がんリスクを理解する上で不可欠である。
(歳) |
| 17,824 | 16,768 | 16,450 | 15,990 | 15,290 | 14,280 | 12,710 | 10,390 | |
| 17,557 | 15,163 | 14,500 | 13,540 | 12,040 | 9,800 | 6,780 | 3,620 | |
| 51,191 | 16,971 | 12,800 | 8,910 | 5,430 | 2,710 | 970 | 100 | |
| 86,572 | 48,902 | 43,750 | 38,440 | 32,760 | 26,790 | 20,460 | 14,110 |
| 33.5 | 61.4 | 64.7 | 67.9 | 71.3 | 74.7 | 78.0 | 81.3 | |
| 28.5 | 16.4 | 14.7 | 12.9 | 11.3 | 9.7 | 8.0 | 6.3 |
| * DS86線量が推定されている人のみ。 |
5.4 白血病リスクは成人期に被爆した集団では生涯存続し、小児期に被爆した集団では過剰リスクは時間の経過と共に減少することが現在のデータにより示唆されている。放射線被曝後における白血病過剰リスクの複雑なパターンを考えると、これを完全に理解するためには調査の続行が必要である。骨髄腫およびリンパ腫の過剰リスクの性質を明らかにするためにも、更なる追跡調査が必要であろう。
5.5 LSSがん罹患データの初めての包括的解析結果は1994年に発表された。これらのデータはがん死亡データを補足する上で重要である。(腫瘍登録は1958年まで開始されなかったので)固形がん罹患の追跡期間は死亡の追跡期間よりも短いにもかかわらず、がん症例数は死亡例数より多い。罹患データは致死率の低い乳がん、甲状腺がん、皮膚がんなどについてリスク推定値を提供し、死亡診断書情報が不完全または不正確なことが多い肝臓がんなどについて調査するのに役立つ。罹患および死亡データの統合を可能にする手順の開発が重要な課題である。腫瘍登録罹患データは既に数々の部位別罹患率調査の基盤として用いられている。また、LSSのがん罹患データを症例対照研究の基盤としてこれまで以上に使用すべきである。
5.6 Sellafield(英国)の白血病症例集積に大きな関心が示されたことからも明らかなように、放射線被曝の遺伝的影響に関連する問題は、一般市民にとっても、また科学的にも重要と考えられている。放影研が調査対象とする原爆被爆者の子供すなわち第一世代(F1)集団は、がんまたはがん以外の疾患による過剰リスクが親の被爆に起因するか否かを検討できる最も強力な疫学調査である。今日まで過剰リスクの証拠は認められていない。しかし、対象集団は比較的若く(1995年現在の平均年齢39歳)、この集団のがんリスク(またはリスクの欠如)を適切に評価するためには今後数十年の追跡が必要である。国際的な放射線防護プログラムによりこの問題がますます注目されており、放影研の前向き調査によって理論的な考察に依存しない確固としたデータが提供されるであろう。
5.7 AHSの価値は他の因子の修飾作用および放射線以外の影響全般を調査することにある。AHSプログラムの最も重要な疫学的役割は、放射線被曝によって罹患率が増加していると思われる動脈硬化症や慢性肝疾患などがん以外の疾患で、後に死亡につながる疾病を監視することであろう。現在これらの疾患を調査するための新しい方法を導入中である。
5.8 AHSでは収集された凍結血清試料110,000件を用いて、ホモシステイン値(冠状動脈疾患との関連が最近示されている)、C型肝炎およびその他の感染など特定の交絡因子が上記疾患の経過に影響を与えたかどうかをそ及的に究明することも可能である。遺伝学的、細胞遺伝学的、放射線生物学的調査の細胞収集源として、また最近ではESR線量推定解析のための歯試料の収集にも、臨床プログラムは役立っている。
5.9 今日までに得られた結果はヒトのゲノムが放射線被曝に対してあまり感受性が高くなく、実際のところ実験用マウスより感受性が低いかもしれないことを示しているが、この問題の解決には今後の調査が必要である。被爆者の子供(F1)の系統的臨床検査は1歳未満の検診以来行われていない。大多数の優性遺伝的疾患および多因子性遺伝病は10歳を超えてから発病し、後者は通常成人期になってから発症する。この分野の調査の実行可能性を検討することは極めて有益である。細胞遺伝学および蛋白質調査が実施された1976-84年に、被爆者の子供の受診率が75-80%と極めて高率であったことを考えると、この集団からの強い関心が期待できる。他の放射線関連の調査に関する報道がF1の人々の疑念をあおっているので、彼らは健康影響について懸念していると考えられる。
5.10 より明確に定義された標識となる表現型を見出すため、現在利用可能なスクリーニング法を用いて、被爆者の子供(F1)集団を対象に、適切な計画に基づく臨床研究を実施すれば、遺伝的な健康障害に関する有益な情報が得られる可能性があり、このような調査の実行可能性について考慮すべきである。この課題に関するワークショップを開催すべきであろう。今後20年の間に被爆者の孫(F2)を調査する必要があるか否かが明らかになると思われるので、現時点でF2調査の実施は勧告しない。
5.11 分子遺伝学的研究により、突然変異が様々な遺伝子部位において子孫へ伝えられたかどうか、またそれらの分子学的変化はいかなるものであるかが究明されよう。論理的に推定されたDS86線量を実証するために、親のリンパ球の細胞遺伝学的調査を勧告する。
5.12 放射線生物学調査は、腫瘍発生に関わる分子レベルの変化を解析することに重点を置くべきである。分子生物学について世界中で急速な進展が見られるので、低線量放射線のリスクをより良く定量化するために、これらの進展を利用して放射線の誘発による腫瘍発生の機序に焦点を当てるべきである。
勧告12
放射線によるがんおよびがん以外の影響について信頼すべき完全な評価ができるように被爆者集団が消滅するまでLSS調査プログラムを継続するよう勧告する。また、AHS調査プログラムは医学的、社会的の両面において、原爆被爆者およびその子孫の健康増進に直接利益となる事業と考える。
勧告13
被爆者の子供(F1集団)の健康についての更なる調査は、特に新しい分子遺伝学的技法を用いた研究と併せて実施すると、遺伝的影響に関する価値ある情報を提供するかもしれないので、これについて検討することを勧告する。
勧告14
発がんの分子学的機序に関して最近開始された研究は、放射線の低線量域における線量反応曲線の形状の究明に重点を置くべきである。
勧告15
放影研には、重要な外科・剖検試料のほか、血清、血漿、リンパ球試料が保存されている。特に、外部での研究のために提供する生物試料の管理と提供に際しての倫理について、明瞭な方針を確立することを勧告する。
6.2 当委員会に示された全般的目標および目的、ならびにそれらの目標達成のために用いられている研究方法は放影研の使命を適切に反映している。これらは時と共に変化してきており、継続的な検討により勧告が出され、特定分野における一連の特別ワークショップによる審議が行われてきた。放影研の研究方法が関連分野における科学的進展に遅れを取らないように、これまで指導的立場を取ってきた理事会に対して敬意を表したい。しかし、より綿密な計画を立て、管理者側が調査プログラム、またその下に位置づけられるサブプログラムおよびプロジェクト、ならびにそれらの相対的優先順位と必要資源をより明らかにすることが現在では普通に行われている。
6.3 計画は様々な形を取り得るが、その本質的な部分は安定した(例えば)5年間の枠組みを提供し、それに基づき放影研の目標を最も的確に反映するような優先順位および資源割り当てに関する研究所としての決定を下していくことである。総合計画は前向きであるべきで、各部におけるプロジェクトが進展し当面の設定目標を達成するかまたは適切な方向転換をする上で、変更に対応できるよう融通性に富んだものでなければならない。その重要な機能の一つは各部の主要な資金レベルを安定したものとし、プログラム管理者が5年先まで確信を持って計画できるようにすることである。この「柔軟な」5か年総合計画を毎年更新し、時間に伴う進展に対応して適切な新しい側面を導入することが期待される。
6.4 全般的な優先順位決定の必要性を示す良い実例は、統計部の役割および適切な資源割り当てに関する評価であろう。本委員会は、同部が研究所全体、特に疫学部と情報技術部に専門的支援を提供しており、さらにDS86線量推定の理解および解釈を進める責務を担っているという説明を受けた。最近の緊縮財政が続く中、同部は少なくとも他の部と同じ程度の人員削減と財政的制約を受けているが、この分野における不足は研究所全体の生産性に不均衡な衝撃をもたらすかもしれない。このような問題は幹部管理者によってのみ検討可能であるので、放影研は同部の役割を慎重に考える必要がある。
6.5 計画目標および了承された当面の目的に対してプロジェクトを日頃から管理するため、さらに新プロジェクトまたは修正プロジェクトに関する提案を公表するため、プログラム管理にはある程度の形式が必要である。肝要な部分は、すべてのサブプログラムおよびプロジェクトに対する定期的な外部審査である。本委員会は、現在放影研専門評議員会が実施している外部審査の過程には限界があり、詳細な評価および指導をするには不十分であるという説明を受けた。
6.6 部レベルでは、了承された当面の目的に照らし合わせて個々のプロジェクトの進行を研究担当理事と毎年検討すること、必要であれば調整を行うこと、適切な当面の目的を設定し直すこと、プロジェクトおよびプログラムの新しい方向づけをあらかじめ示すことが必要であろう。
6.7 有効であることが判明しているもう一つの機構は、すべての部の幹部職員(部長を含む)から成る内部審査委員会であり、この委員会は了承された当面の目的に照らし合わせて各部のプロジェクトを適宜検討し、その評価結果を研究担当理事に報告する。このような手順は、他の部の職員の研究を理解し、自身の研究が放影研全体の目標の中でどのように位置づけられるかを認識する上でも役立つと考えられる。
結論
6.8 放影研のような調査環境におけるプログラム管理は、その手順が形式的で高圧的になることによって新しい考えの発展を妨げないような巧妙なものでなければならない。しかし、他機関における経験によれば、現在の(世界全般の)資源節約傾向の中で最良の結果を得るためには、全般的な総合計画およびかなり詳細な調査プログラム管理の確固たる実施が必要である。実際には、この総合計画を各部に通達し、各部は全般的な目標にかんがみてそれ自身の優先順位および調査プログラム管理計画を明示する。総合計画と各部の計画は互いに関連し、各部の経験および思考が総合計画に生かされ、また各部で総合計画が共有される。
6.9 放影研調査プログラムの生産性の維持および成功のためには、各分野から選ばれた専門家の委員会が5年に一度各調査プログラムを審査するように、外部専門家による集中的な審査手順を確立することが重要である。外部審査委員会が、個々の研究計画を評価して研究者と共にそれらを検討し、調査プログラムの将来方向について勧告が行えるように時間を設けるべきである。この機構により、特定分野の著名な専門家による集中的批判および討議がなされることが刺激となり、研究者はプロジェクトの向上に努めるだけでなく、生産性の低いプロジェクトの停止も検討するであろう。
勧告16
現在の組織構成において5か年総合計画を立て、それを毎年更新し、役員会を通して理事会の承認を得ることを勧告する。
勧告17
また、各部を5年ごとに検討する国際的専門家グループによる新しい審査手順を確立し、例えば各グループの委員長を専門評議員会の異なる委員が務めることを勧告する。
勧告18
専門評議員会が放影研の評価および指導においてより積極的な関与をし、より活発な役割を担うことを勧告する。その構成は、放影研の研究に関係するすべての主要分野を反映すべきである。さらに、評議員の任期は5年として再選は一回のみとし、毎年2人が交代するような方式を勧告する。
7. 国内および国際協力
7.1 現在、放影研には強力で有能な指導者ならびに熟練した支援職員がいる。(特に統計・疫学において)削減による欠員を補充する融通性および力量を持つ安定した幹部が不可欠である。放影研の問題の一つは、終身雇用制により比較的固定した職員集団が予測可能であるという日本の機関における慣習に起因している。これは明らかに利点もあるが、放影研プログラムに影響を与え得る基礎科学の新しい発展に対する放影研の迅速な反応を妨げるという点において、またそれに必要な人員採用を制限するという点においてこの慣習には制限もある。恐らく大学との協力により、日本国内の人材の短期雇用を可能にする手順を確立することは放影研にとって有益であろう。
7.2 特に、広島・長崎などの大学またはその他の研究機関との連携を強化することが適切かもしれない。数多くの独創的な研究を行うための十分なデータがあるので、大学院の学生が放影研の研究活動にかかわる可能性が出てくるであろう。放射線に関連する、または関連しない研究の両方において数学・物理学・生物学・疫学・医学上の連携が期待される。広島と比較して、長崎放影研では既に長崎大学との連携が存在しており、両機関の研究者が共同で論文をまとめている。
7.3 広島県知事は広島市にがんセンターを設立することを考えている。これが進めば、疫学および臨床部門の将来の研究実施において放影研の参画は有益である。
7.4 特定のプロジェクトに関する研究は、日本の研究フェローシップまたは、例えば、EC委員会の研究理事会などから資金を獲得することが可能かもしれない。ECには電離放射線の健康影響に関する研究プログラムがあり、既に旧ソビエト連邦におけるプロジェクト支援にかかわっている。放影研の貴重な専門知識を役立て、チェリヤビンスクおよびマヤークにおける職業上または一般の被曝集団データベースから確証的データを引き出すために放影研での研究との調整を図ることは論理にかなっていると考えられる。これにより、放影研は日本・ヨーロッパ・米国からの支援を受け国際化すると本委員会は確信する。本委員会が説明を受けた特定の問題で、特に米国側の協力に影響を与えるものとして、放影研で任期を終え帰国した者が米国での再就職の見通しが立てにくい点が挙げられた。これは、研究者の国際的な移動が頻繁にある欧州連合の状況とは対照的であると本委員会は考える。
7.5 一年に、100人以上の科学者が2-3日ずつ放影研を訪れるような慣習を続行することは、有益でもなく実際に効率の低下につながるものと本委員会は考える。これらの科学者が学び得るものは不十分で、職員の研究プログラム実施の妨げにもなる。数少ない科学者のより長期間で系統立った交流の方が有効であろうが、有能な者を慎重に選出することが不可欠である。
結論
7.6 放影研は放射線調査の中心的機関として国際的に知られているが、その多様な調査プログラムの結果は日本および世界中の学界により広く公表する必要がある。放影研の中心的調査プログラムおよび共同調査を続行するために、有能で意欲的な研究職員を採用・維持することが不可欠である。日本の他機関の人材を短期的に雇用すること、特に地元の大学との関係を強化すること、海外の機関との正式な協定を新たに締結することが有益である。
勧告19
日本の大学または他の研究機関、特に広島・長崎の大学との正式な連携関係を確立または強化し、放影研の部長が客員教授を務め、教べんを執ると共に、大学院の学生が放影研プロジェクトにかかわることを考慮するよう勧告する。
勧告20
放影研が、日米二国間の研究者交流に加えて、他国および地域的または国際的機関との研究者交流のための正式プログラムを確立することを検討するよう勧告する。
勧告21
放影研に蓄積されている知識からみて、放射線リスクに関する一般の理解を深めるための情報センターとして放影研を発展させることを勧告する。
第3章 調査集団 (3.4)
放影研の集団調査は、かくも多数の人が被爆したというだけではなく、各個人に関して記録されている情報の質が極めて高いという点でも他に例を見ない調査である。電離放射線の健康への影響をこのような詳細な形で調査できる機会が将来訪れるとは思えず、またそのような機会があったとしても、放影研に現存するだけの情報を収集するには更にもう50年を要するであろう。
第4章 学術的検討
(i) 疫学 (4.12)
疫学部が保有するデータは、放射線の健康への影響を評価するためだけではなく、様々な生活様式因子がもつ健康への影響および同因子と放射線被曝との相互関係を決定するために大変重要である。現在、データを解析し、発表するための努力は不十分であり、これまでに収集され将来的に価値のある情報が十分に活用されていない。
勧告1
疫学部は死亡およびがん罹患に関するデータを引き続き収集すべきであり、この作業は強化されるべきであると勧告する。データの量と範囲からみて、放影研の管理者はこれらの調査を最優先すべきである。更に、既に収集済みの将来的に価値があると思われる情報を解析するために国内、海外の他の研究所の疫学者と共同して調査を遂行するべきである。 (ii) 統計 (4.18)
優れた調査が統計部で行われており、研究所全体の大きな活力源となっている。同部の貢献は、蓄積されたデータセットを世界レベルのヒト放射線リスク推定の基盤とするためには必要不可欠のものである。
勧告2
統計部は疫学部と協力して放射線被曝リスクの解析を引き続き行うこと、また統計部門における質の高い調査研究を維持すべきことを勧告する。
勧告3
統計部は、引き続き他の研究グループが死亡率および罹患率に関する基礎データセットを解析に使用できるようにすることを勧告する。同様に、精神遅滞、IQ、その他胎内被曝に関連した調査結果などに関するデータセットも利用できるようにしていくべきである。
(iii) 情報技術 (4.27)
効率の良いデータ管理およびコンピュータ処理は、放影研の調査の成功の基幹となるものである。委員会は、放影研がコンピュータ基礎構造について正しい方針決定を下し、同部は優秀な技能および英知をもってその決定実行に取組んできたと考える。中央連結型データベースの構築において過去数年間見られている進歩には目を見張るものがある。
勧告4
数十年にわたり収集された大量のデータが正しく保存、記録され、放影研の研究員がアクセスできるようにすることは大変重要であるので、情報技術部に引き続きゆるぎない支援を与えることを勧告する。
(iv) 臨床研究 (4.37および4.38)
本調査プロジェクトの重要性は、LSSおよびAHS集団の追跡調査の規模と質、LSSおよびAHSと関連して行われている疫学および統計学調査の質ならびに胎内被爆者の継続的評価に反映されている。臨床研究部の役割は全ての部門の多くの目標の達成に不可欠である。
本調査プロジェクトの内容と質は、臨床研究部が他のすべての部門に対して行っている次のような協力に反映されている。
- 致死性および非致死性がんならびに放射線被曝のがん以外の疾患に及ぼす影響についての臨床データの提供
- LSS集団に認められた種々の関連性についての詳細な調査
- 他に類を見ない、血清、血漿およびリンパ球試料の提供
- 被爆者への重要な「掛け橋」的役割
勧告5
臨床調査プロジェクトの多くは今後も続行すべきであるが、調査プログラムを厳密に検討し、成果が得られないと思われるものは中止することを勧告する。1945年には子供で、現在成人に達している人については、放射線感受性が若年被爆者で最も高いと思われるので、調査を継続すべきである。
勧告6
AHSは被爆者の福祉のために極めて重要であり、放影研に対する被爆者の非常な協力を可能にしたと考えられるので、この観点から重要なサービスの継続を勧告する。被爆者の高齢化が進んで、健康問題は更に複雑となっており、高い受診率を維持するための配慮が必要である。
(v) 遺伝学 (4.47および4.48)
分子生物学的研究は最も詳細な測定を可能にし、将来の研究の焦点となるであろうが、被爆者の子供(F1)の健康については従来の調査を継続し、更には拡大することが必要である。また、分子学的研究が放射線による多因子性遺伝障害の問題の解決に近づくのはどの時点であるのか明瞭ではないので、従来の調査は今後も重要である。
被爆位置における、現在改善されつつある物理学的線量測定および個人データと染色体データ、歯のデータならびに建築材料、陶磁器、宝石といったその他の資料についての固体線量測定データとをより密接に関連付けることができるようになった。従来、線量測定は放影研の活動ではないが、新しく認めれたこのような関連性はDS86線量体系の検証に極めて重要である。 勧告7
被爆者の子供(F1)の健康に関する調査は、多因子性疾患についてのデータを提供するかもしれないし、また被爆者とその子供に直接恩恵を与えると考えられるので、今後も継続するよう勧告する。
勧告8
生物試料に基づく線量推定値と物理学的線量推定値との比較に必要なFISH分析およびESRのための生物試料の保存、ならびにこれら試料についての記録作成を勧告する。
勧告9
将来の分子遺伝学研究のための生物試料の保存、ならびに保存試料についての記録作成の続行を勧告する。
勧告10
細胞遺伝学における最も進んだ方法および専門知識・技術を今後も放影研に導入することを勧告する。
(vi) 放射線生物学 (4.53および4.57)
分子生物学の進歩にかんがみ、原爆被爆者から得られ、保存されている腫瘍試料および正常組織試料は極めて重要であり、保存試料の拡大と維持は放影研の主要な任務である。
放影研における免疫学研究の特徴は、加齢の影響ならびにT細胞の免疫能への加齢と放射線被曝の同時効果を調べるのに十分な長さの期間にわたって原爆被爆者についての調査が繰り返し実施されているということである。クローン性拡大に関する最近の研究は特に興味深い。
体細胞突然変異測定系は放射線被曝が最近であれば使用できるが、体細胞突然変異は、はるか以前に生じた放射線被曝についての信頼できる情報を提供できる程持続的ではない。
疫学調査における因果関係の確立には、強力な関連性の他に幾つかの条件が必要である。なかでも、「もっともらしい機序」を仮定することが重要である。メカニスティックモデルにより行うこの仮定は、観察を超えた外挿、特に低線量被曝の場合の外挿の基盤ともなる。
従って、放影研における放射線リスクの調査は、明示的にも暗示的にも、常に機序とモデルに関連して行われることは明瞭である。分子遺伝学に基づく発がん過程についての知識の飛躍的な増大は、モデルがこの方向に進むことを示唆している。放影研にモデルについての専門家を配置することは妥当でないと思われるが、実験研究から得られたデータが放影研の研究戦略に影響を与えると思われるので、その意味を常に考慮することが極めて重要である。
勧告11
放射線生物学部は分子疫学と免疫学に重点を置き、発がん過程のモデル作成に関与している世界中の研究グループと放影研とが強力に連携することを勧告する。
第5章 将来計画
勧告12
放射線によるがんおよびがん以外の影響について信頼すべき完全な評価ができるように被爆者集団が消滅するまでLSS調査プログラムを継続するよう勧告する。また、AHS調査プログラムは医学的、社会的の両面において、原爆被爆者およびその子孫の健康増進に直接利益となる事業と考える。 勧告13
被爆者の子供(F1集団)の健康についての更なる調査は、特に新しい分子遺伝学的技法を用いた研究と併せて実施すると、遺伝的影響に関する価値ある情報を提供するかもしれないので、これについて検討することを勧告する。
勧告14
発がんの分子学的機序に関して最近開始された研究は、放射線の低線量域における線量反応曲線の形状の究明に重点を置くべきである。
勧告15
放影研には、重要な外科・剖検試料のほか、血清、血漿、リンパ球試料が保存されている。特に、外部での研究のために提供する生物試料の管理と提供に際しての倫理について、明瞭な方針を確立することを勧告する。
放影研のような調査環境におけるプログラム管理は、その手順が形式的で高圧的になることによって新しい考えの発展を妨げないような巧妙なものでなければならない。しかし、他機関における経験によれば、現在の(世界全般の)資源節約傾向の中で最良の結果を得るためには、全般的な総合計画およびかなり詳細な調査プログラム管理の確固たる実施が必要である。実際には、この総合計画を各部に通達し、各部は全般的な目標にかんがみてそれ自身の優先順位および調査プログラム管理計画を明示する。総合計画と各部の計画は互いに関連し、各部の経験および思考が総合計画に生かされ、また各部で総合計画が共有される。
放影研調査プログラムの生産性の維持および成功のためには、各分野から選ばれた専門家の委員会が5年に一度各調査プログラムを審査するように、外部専門家による集中的な審査手順を確立することが重要である。外部審査委員会が、個々の研究計画を評価して研究者と共にそれらを検討し、調査プログラムの将来方向について勧告が行えるように時間を設けるべきである。この機構により、特定分野の著名な専門家による集中的批判および討議がなされることが刺激となり、研究者はプロジェクトの向上に努めるだけでなく、生産性の低いプロジェクトの停止も検討するであろう。
勧告16
現在の組織構成において5か年総合計画を立て、それを毎年更新し、役員会を通して理事会の承認を得ることを勧告する。
勧告17
また、各部を5年ごとに検討する国際的専門家グループによる新しい審査手順を確立し、例えば各グループの委員長を専門評議員会の異なる委員が務めることを勧告する。
勧告18
専門評議員会が放影研の評価および指導においてより積極的な関与をし、より活発な役割を担うことを勧告する。その構成は、放影研の研究に関係するすべての主要分野を反映すべきである。さらに、評議員の任期は5年として再選は一回のみとし、毎年2人が交代するような方式を勧告する。
第7章 国内および国際協力 (7.6)
放影研は放射線調査の中心的機関として国際的に知られているが、その多様な調査プログラムの結果は日本および世界中の学界により広く公表する必要がある。放影研の中心的調査プログラムおよび共同調査を続行するために、有能で意欲的な研究職員を採用・維持することが不可欠である。日本の他機関の人材を短期的に雇用すること、特に地元の大学との関係を強化すること、海外の機関との正式な協定を新たに締結することが有益である。
勧告19
日本の大学または他の研究機関、特に広島・長崎の大学との正式な連携関係を確立または強化し、放影研の部長が客員教授を務め、教べんを執ると共に、大学院の学生が放影研プロジェクトに関わることを考慮するよう勧告する。
勧告20
放影研が、日米二国間の研究者交流に加えて、他国および地域的または国際的機関との研究者交流のための正式プログラムを確立することを検討するよう勧告する。
勧告21
放影研に蓄積されている知識からみて、放射線リスクに関する一般の理解を深めるための情報センターとして放影研を発展させることを勧告する。
| 委員長 | Roger H. Clarke 英国放射線防護庁総裁 Chilton Didcot, Oxfordshire UK |
||||||||
|
|
|||||||||
| 委 員 |
|
||||||||
|
|
|||||||||
| 技術補佐 | Colin R. Muirhead 英国放射線防護庁 Chilton Didcot, Oxfordshire UK |