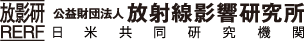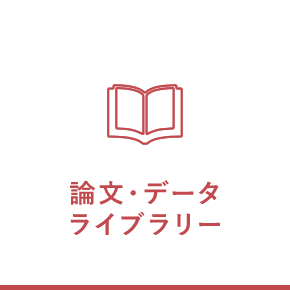放影研寿命調査における癌以外の疾病による死亡率、1950-1985年
1950年から1985年の寿命調査死亡率の解析で、高線量群に癌以外の疾病による死亡に過剰リスクが観察された。
放影研疫学部 清水由紀子、国立水俣病研究センター 加藤寛夫、放影研常務理事 William J Schull、米国立環境保健科学研究所 David G Hoel
この記事は RERF Update 3(2):3-4, 1991に掲載されたものの翻訳です。
原爆傷害調査委員会(ABCC)とその事業を引き継いだ放射線影響研究所(放影研)は、1950年以来、原爆放射線が死亡率に及ぼす影響を究明するために被爆者の固定集団と比較対照群の、いわゆる寿命調査(LSS)集団の調査を行ってきた。その調査結果は定期的に解析が実施されている。
最近、1950年から1985年のLSS集団の死亡率が求められ、DS86新線量を使った癌による死亡率の解析結果が報告された(清水ら、放影研業績報告書12-87、5-88)。その報告では、各部位の悪性疾患の増加と放射線との関係を示す知見が引き続き認められた。しかし、癌以外の死因による死亡率も増加しているかどうか、また、他の死因による寿命短縮があるかどうかはこれまで、はっきりしていない。癌以外の死亡率についての以前の解析(最近のものとしては加藤ら、放影研業績報告書5-81を参照)では、そのいずれの可能性についても証拠を示すことはできなかった。しかし、T65線量で4グレイ(Gy)以上の高線量群では、癌以外の死因による死亡率が上昇しているようにみえることが指摘されていた。前回の解析以来、更に7年の追跡調査資料の追加があり、また新線量を使った解析の結果によれば、高線量群、すなわち2Gy以上で、癌以外による死亡の過剰リスクの徴候が、よりはっきりと観察された(清水ら、放影研業績報告書2-91)。それについてここで簡単に述べる。
LSS対象者 120,128人(被爆者93,611人、対照者26,517人)の中で、DS86線量推定値が求められているのは 75,991人であり、これはDS86サブコーホートと呼ばれている。このサブコーホートにおける 1950年から1985年の死亡者 28,737人のうち、死因不明が 75人、外死因が 1,515人、新生物が 6,224人、血液疾病が 146人であった。「新生物と血液疾病以外の疾病」による残りの死亡者 20,777人が今回の解析の対象であった(表参照)。血液疾患による死亡の診断の正確性は非常に低く、白血病や悪性リンパ腫が含まれていることが多い。したがって、血液疾患は今回の解析から除外し、ここで「癌以外」とは、新生物と血液疾患以外のすべての疾病をさす。表に癌以外の死亡者数を特定死因別に示した。死亡者の約半数は循環器系の疾患であった。
|
表. 1950年から1985年のDS86サブコホート75,991人における死因別死亡数
|
| 死因 | 死亡数 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1950年から1985年における癌以外の死亡率は、有意な非線形の線量反応を示し、2ないし 3Gy以上の線量で過剰危険率がみられる(図1)。統計学的には、単純な線形モデルよりも純粋な二次曲線または線形閾値モデルの適合が良好である(線量の推定閾値は 1.4Gy、信頼限界は 0.6-2.8Gy)。全体としては、癌以外の死亡率の増加は、1966年以降、被爆時年齢が若い被爆者(40歳以下)において統計学的に証明され、この年齢群に感受性があることを示唆している。特定死因別にみると、2Gy以上の高線量で循環器系の疾患(脳卒中と心臓疾患)と消化器系の疾患(特に肝硬変)の過剰相対危険率が、被爆時年齢が若い被爆者(40歳以下)において、最近(1966-1985年)みられる。この循環器系疾患に関する知見は、特定の診断基準、剖検材料、死亡診断書や心電図結果を含む臨床所見に基づいて行われた心臓血管疾患(CVD)発生率調査によって支持されている。
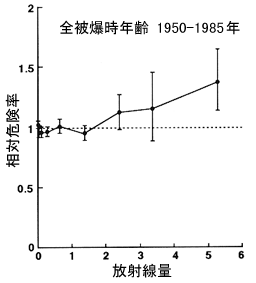
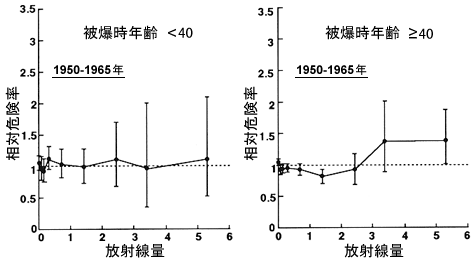
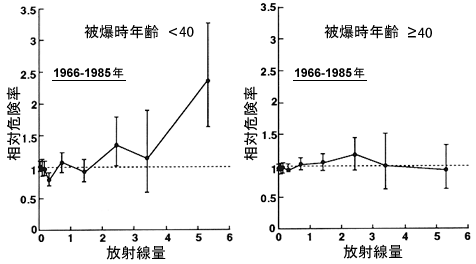
図1. 新生物と血液疾患を除くすべての疾病による死亡率の線量反応曲線。全期間について適合度が最も良好な線量反応モデルは、二次曲線または線形閾値モデルである。観察された過剰死亡数は、被爆時年齢が若い被爆者で、しかも主として最近の期間にみられる。初期には、被爆時年齢が高い被爆者にU字型の線量反応(低線量では下降線、高線量では上昇線)がみられた。(相対危険率の90%信頼区間を棒で表示した。)
癌以外の死亡の危険率増加は、癌に比べてはるかに低い。全例における 2Gyでの相対危険率は、癌以外の死亡で 1.06(線形閾値モデルに基づく)、癌死亡で 1.78(線形モデルに基づく)である。104人年Gy(PYGy) あたりの過剰死亡数は、癌以外で 1.2、そして癌で 10.0である。被爆時年齢が 40歳以下で 1966年から1985年の間に死亡した被爆者では、2Gyでの相対的危険率は、癌以外の死亡で 1.19、癌で 2.06であり、104PYGy当たりの過剰死亡数は、それぞれ 1.7および 11.2である。
年齢別死亡率の対数である Gompertz関数 によって、成人におけるほとんどの慢性疾患の死亡率を十分に表わすことができるとされている。年齢別死亡率の対数は直線となり、Gompertz関数 の上昇は寿命の短縮を示唆する。図2 では、被爆時年齢 40歳未満と 40歳以上に分けて、2Gy以上の被爆者における癌以外の年齢別死亡率の対数を対照群(0Gy)と比較した。前者の年齢群では、0Gy群と比べて 2Gy以上群の癌以外の年齢別死亡率は上昇している。他方、被爆時年齢 40歳以上の群では、Gompertz曲線 の上昇はみられない。
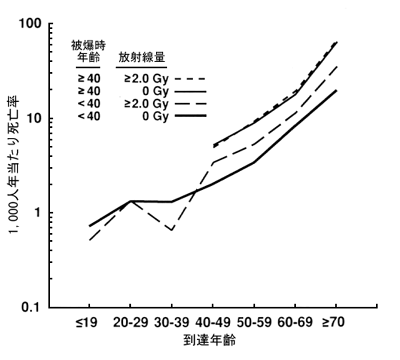
図2. 新生物と血液疾患以外の全疾病の年齢別死亡率
(1,000人年当たり)、放射線量および被爆時年齢別。
放射線の癌誘発に及ぼす影響(おそらく確率論的現象)と、癌以外による死亡率に及ぼす影響との間に相違があり、後者は、線量に閾値がある非確率論的過程に従うであろうと推測することは非合理的ではない。しかし、アテローム性病変での転換遺伝子について最近の証拠が得られていることを考えると、CVDの増加は特に興味ある所見であり、その関連が本当であれば、アテローム性動脈硬化症に対する電離放射線の影響は確率論的現象として扱われるべきことを示唆するであろう。この件に関しては、今後のデータについて特に興味がもたれる。
ここに述べた所見は、死亡診断書に基づくものであるので限界がある。その中でおそらく最も顕著なものは、放射線に関連した癌による死亡が他の死因として、誤って報告される可能性があるということである。成人健康調査で得られた臨床データや入手可能な剖検、腫瘍登録データを利用して、癌以外の死亡で観察された相対危険率の増加に対して、このような誤りの影響を調べた。現在では、高線量での癌以外の死亡にみられる増加に対するこのような誤りの寄与については、満足できるほど明確な推定はできない。しかし、現在でも、誤診断ということだけでその増加をすべて説明できないように思われる。剖検データを使って誤診断の影響のきっちりした統計解析が行われたが、癌以外の死亡にみられた有意な線量反応が、癌の誤診断ということでは簡単に説明できないという結論が出ている(Sposto ら、放影研業績報告書4-91、RERF Update 3(2):5, 1991を参照)。
A Stewart と G Kneale の淘汰効果説(Health Phys 58: 729-35, 1990)を支持するような幾つかの証拠がみられる。しかし、その証拠は、調査の初期において被爆時年齢の高い人に限られる。被爆時年齢が 40歳以上で、1950年から1965年の間の死亡者では、癌以外の死亡にU字形の線量反応(低線量では下降線、高線量では上昇線)がみられた(図1)。放射線誘発癌(白血病以外の)は、主として後期にみられるので、淘汰は癌の危険率に対してはっきりとわかるほどの影響を及ぼすことはない。
このLSS集団における死亡率と罹病率調査サブサンプル(成人健康調査)の2年に一度の健康診断を通じて明らかになる疾病については、今後も追跡調査を続け、癌以外による死亡の増加と放射線との関係が示唆されていることの確認と、高線量原爆被爆者においてそのための寿命短縮があるかどうかの決定が必要である。