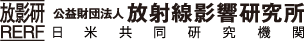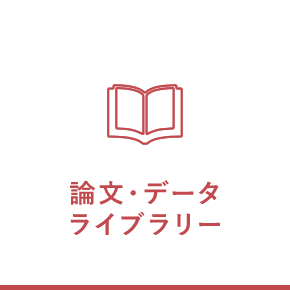物理学的線量測定と生物学的線量測定
広島の被爆者における歯エナメル質の電子スピン共鳴法(ESR)による線量推定データと細胞遺伝学的データの比較
放影研遺伝学部 中村 典
この記事は RERF Update 9(1):3, 1998に掲載されたものの翻訳です。
原子爆弾によるガンマ線被曝線量の推定を目的として、広島の原爆被爆者から提供された 100個の歯試料を電子スピン共鳴法(ESR)を用いて調査した(中村ら、1998)。頬側の歯表面に影響を及ぼすことが多い歯科X線治療による被曝の影響を考慮しないといけないと思われたので、個々の歯を頬側と舌側に分割し、それぞれのエナメル質を分離し、ESRによる線量測定を行った。その結果、約20個の歯試料については、舌側部分よりも頬側部分の被曝線量の方がかなり高く、これは歯科X線被曝による影響が無視できないことを示すものではないかと思われた。しかし詳しく検討してみると、舌側と頬側で線量の異なる試料の多くは門歯と犬歯であった。歯科X線被曝がもっぱら前歯のみに影響するとは考えにくく、紫外線被曝がESR信号の原因となると報告されていることを考えると、得られた結果は概ね、太陽光線被曝に起因すると思われる(Romanyukhaら、1996年)。
次に 69人の歯試料提供者中 61人について細胞遺伝学的検査が行われ、得られた結果をESRによる推定値と比較した。リンパ球の転座頻度と、臼歯の頬・舌側および前歯(すなわち門歯と犬歯)の舌側についてみると、ESRにより推定された被曝線量は、試験管内ガンマ線照射実験から期待されるものと同様の線量反応関係を示した(図1)。しかし、前歯の頬側試料については、ESRにより推定された線量の割には、実際の転座頻度ははるかに少なかった。これは太陽光線による影響で歯の被曝線量が過大推定されているためである(図2)。
同じ歯の頬側と舌側の平均線量を比較すると、その差は第一門歯で最大であり、口中の歯の位置が奥になるほど少なくなった。すなわち、第一門歯では 0.5Gy、第二門歯では 0.3Gy、犬歯・小臼歯では 0.2Gy、親知らずを含む大臼歯では 0.04Gyであった。前歯の舌側も、頬側ほどではないにしろ、太陽光線被曝による影響を受ける可能性があるので、これら頬側部分の過剰線量は、太陽光線被曝に起因する最小限度の推定線量値であると考えられる。
結論としては、歯のエナメル質を用いたESR測定と血液リンパ球の細胞遺伝学的検査のいずれも過去における個人線量推定に有用と考えられる。慎重を期するためには、前歯は測定しないか、またはもし前歯を用いる際には太陽光線に起因するESR信号を除外する努力が必要である。
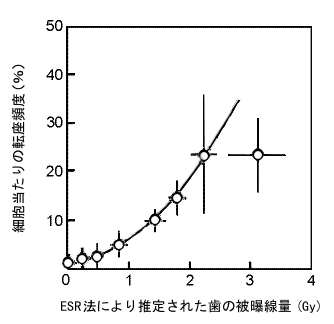
図1. 原爆からのガンマ線以外の因子による影響が最も少ないと考えられる
臼歯舌側部のESR推定線量と歯の提供者リンパ球における転座頻度との関係
各点は、5人の平均値を示し、それに交差する線は平均値の標準偏差を示す。曲線は期待される線量反応であり、FISH法で測定された転座頻度(Lucasら、1995年)の70%に相当する(今回の調査で使用されたギムザ染色では転座の30%が見落とされることがわかっているため;大瀧ら、1982年)。
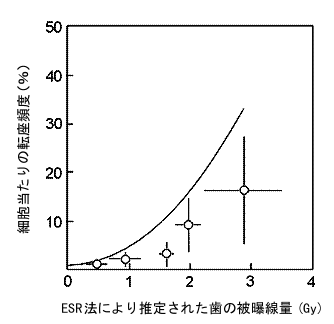
図2. 太陽光線被曝による影響が最も大きいと考えられる
前歯頬側部のESR推定線量と転座頻度との関係。
このテーマについての参考文献