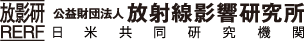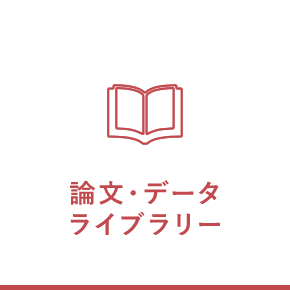歯エナメル質による放射線量の推定
被爆者から提供された抜去歯の電子スピン共鳴測定値は、同じドナーのリンパ球染色体異常頻度に非常によく相関する。
中村 典、1 岩崎みどり、2 宮沢忠蔵、3 秋山實利、4 阿波章夫1
放影研 1遺伝学部、4放射線生物学部 奥羽大学歯学部 2放射線歯学科、3予防歯学科
この記事は RERF Update 6(2):6-7, 1994に掲載されたものの翻訳です。
放射線の「フィンガープリント」は、かなり長い間、特定の資料の中に残存している。例えば、原爆被爆40年余り後に広島、長崎の屋根瓦を用いて原爆のγ線量を測定するために、熱ルミネッセンスが使用されてきた。
電子スピン共鳴法 (ESR)(電子常磁性共鳴法とも呼ばれる) として知られる技法では、放射線により生じたラジカル(不対電子)は、特定の磁場力を受けると、マイクロ波を吸収する性質を利用する。ラジカル(原子または分子)は、その種類によってマイクロ波を吸収する磁場強度が異なる。液体では、ラジカルはすぐに消えてしまう。しかし固体、例えば骨や歯などの人体の石灰質化された組織などでは、ラジカルは自由に動けず、ずっと安定している。骨は常に作りなおされ、利用もすぐにはできないことから、主に歯が今日のESR研究に用いられてきた。(しかし、不慮の被ばく後、放射線壊死により切断された脚の骨から得られたESR線量推定が報告されている[Desrosiers,Health Phys 61:859-61, 1991]。)歯の表面を覆っているエナメル質は、ほとんどハイドロキシアパタイト(カルシウムおよびリン酸塩で構成される結晶構造の化合物)でできており、新陳代謝がまったくない。歯エナメル質は人体における無機物として特異なものといえる。
ESRについての実験研究が1960年代から出版されているが、この10年間に、ESRは新たな注目を浴びるようになってきた。日本では、大阪大学の池谷氏が積極的にESR研究を進めてきた(池谷ら、日本応用物理学会誌23:697-9, 1985;石井および池谷、日本応用物理学会誌29:871-5, 1990など)。主に長崎の被爆者から得た歯エナメル質の一連のESR研究が、長崎大学の岡島氏の研究班により出版されてきた(巽ら、広島医学41:382-5, 1988、J Radiat Res 29:88, 1988 [英語要旨])。しかしこれらの結果と、個々人の1986年線量推定方式(DS86)推定線量との比較は行われていない。
歯エナメル質のESRについて現在分かっていること
・CO33- ラジカルが測定されているように思われる。
・光量子-エネルギー依存が明らかである。例えば、40 keVのX線は、コバルト60のγ線の5倍以上の単位線量あたりのESR信号を産み出す(巽ら、広島医学39:418-22, 1986;岩崎ら、ラジオアイソトープ40:421-4, 1991)。
・γ線と比較すると、ESR信号発生に関し、中性子の効果はずっと低い(巽、フィルムバッジ・ニュース125:1-9, 1986;岩崎ら、出版されていない資料, 1991)。
・観察されたESR信号の強度は、調査したエナメル質の質量に正比例する(岩崎ら、奥羽大歯学誌17:95-100, 1990)。
・225-0.33 R/分の範囲の線量率のγ線試験管内照射では、線量率効果は観察されなかった(岩崎ら、ラジオアイソトープ41:642-4, 1992)。
・試験管内でのエナメル質標本の放射線照射により、乾燥した状態でも水中でも、生じたESR信号の強度は同じであった。(同上)。
・直径0.5-1.4mmのエナメル質粒子の大きさが好ましい(岩崎ら、ラジオアイソトープ42:470-3, 1993)。
広島ESRプロジェクト
広島では、1986年に、放影研の成人健康調査対象者に抜去歯の提供をよびかけ始めた。それ以来、300本の歯が収集されたが、そのうち 約3割がエナメル質分離およびESR測定に適していることがわかった。
我々は、象牙質は大きなバックグラウンド信号を発生し、放射線関連の信号を発生させるにはほとんど役に立たないので、エナメルを注意深く象牙質から分離しなければならないことを学んだ。現在、歯を薄く切った後エナメル質を分離するために、流水式のディスク形のダイヤモンド・カッターが使われている。食パン一切れから皮の部分を薄く切ることを想像していただきたい。この方法は、退屈で、大変な技術が必要であるが、極めて良好な結果が得られる。(この方法については、将来その詳細を説明する。)
1つ未解決の問題は、歯科用X線(有効エネルギーが30 keV以下である)の線量への寄与をどのように評価するかということである。前述のように、このような低エネルギーの光量子は、コバルト60のγ線よりもはるかにESR信号を生じる能力が高いので、実際に線量にはほとんど寄与していないのに、ESR信号には寄与があるかもしれない。歯科用X線量を推定するため、それぞれの歯を内側と外側の部分に分割した。以前はパノラマ写真は一般的ではなかったので、診断用歯科用X線は、大半が歯の外側にあてられたと推測している。歯の内側よりも外側により大きなESR信号が見られる場合には、そのドナーの結果を解釈する際に特に注意を払う必要がある。
10人のドナーからの11の歯についての予備的な結果を 図 に示してある。現在のESR測定値は、試験管内γ線照射を行っていないものである。したがって、それぞれの歯の放射線感受性が異なっているかもしれないので、ESR結果は必ずしも線量に正比例しているとは限らない。しかし、幾つかのおもしろい特徴が明らかである。まず、線で結んだ2つの黒丸は、同じドナーからの2本の歯の結果を表している。2本の歯の内側半分はほとんど同一の信号強度を示しており(図には示していない)、図の中の低い値に近かったので、この相違は、ほとんど歯科用X線に由来しているようである。次に、染色体異常のデータとESRデータとはよく一致している。第3に、1つだけ例外がある。DS86推定線量が 1.3 Gyで染色体異常のリンパ球頻度が 35%であった被爆者の歯が、放射線被ばくの兆候をまったく示していなかったのである。その標本は、他の歯よりずっと後になって形成されることが知られている親知らずであり、歯のドナーは被爆時年齢が 15歳であった。親知らずの発達における個人の差異はかなり大きいので、その歯が 1945年の被爆時に本当に未発達であったかどうかはわからない。将来、このドナーからの別のタイプの歯を調査をしたいと願っている。
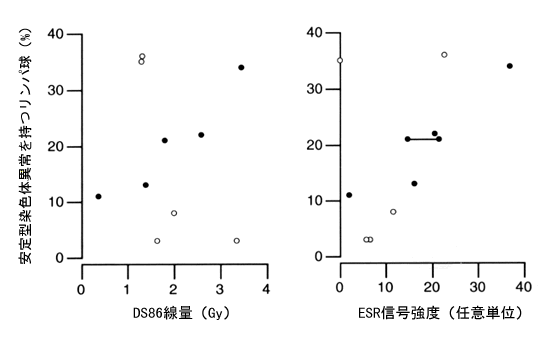
図. 左:安定型染色体異常を持つリンパ球の頻度を1986年線量推定方式(DS86)総線量に対してプロットしたもの。右:安定型染色体異常を持つリンパ球の頻度をESR信号強度に対してプロットしたもの。
それぞれの歯のエナメル質の量が異なるので、測定した信号強度を重量で割って補正した。黒丸は、我々の大きなコホートにおける染色体異常線量反応の平均に近い値を示した5例である。線で結んだ二つの黒丸は、同一ドナーからの2本の歯の結果である。5つの白丸は、例数は少ないが、いわゆる平均から大きくずれている例である。ここに示すESR信号は、歯の外側半分のものである。
展望
例えば初期のホモサピエンスの歯(Tiemeiら、Nature 368:55-6, 1994)の年代を算定するためにESRが利用できるという観点からすると、歯エナメル質は、非常に低線量率で与えられた放射線量を適切に蓄積できるようである。これはつまり、ヒトの歯は、急性放射線被ばくだけでなく、放射線作業員や汚染環境に居住する人々が受けるくり返しの低線量被ばくまたは慢性的γ線被ばくにとっても、すぐれた自然の生体線量計かもしれないことを意味する。放影研では、歯エナメル質のESR法と、蛍光in situハイブリダイゼーション法を用いたリンパ球染色体異常の研究を組み合わせて調査を行っていく予定である。