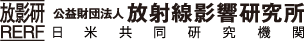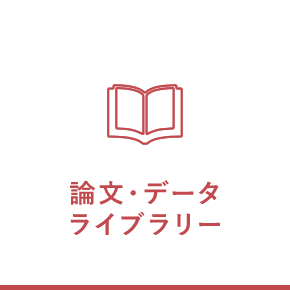成人健康調査におけるコレステロール値、1958-1986年
成人期における総血清コレステロール値の変化を数世代にわたって調査した結果、総血清コレステロール値の上昇という好ましくない傾向が認められた。これは、女性原爆被爆者において冠動脈性心疾患による死亡率が増加している一因と考えられる。
放影研臨床研究部 山田美智子
この記事は RERF Update 5(4):5-6, 1993に掲載されたものの翻訳です。
原爆被爆者を対象とする成人健康調査(AHS)集団の長期追跡調査では、1958年以来 2年ごとに行われてきた測定で、若者から高齢者まで 約1万人の総血清コレステロール(TC)の測定値など、疫学研究のための膨大な情報を収集している。これらのデータは、30年間にわたる日本人集団のTC値の長期的な変化だけでなく、電離放射線被ばくとTCとの関係をも解明する貴重な機会を提供する。
対象者および方法
今回の調査対象者は、1958年から1986年までの間に少なくとも1回検診を受けたことのある男性3437人(広島:2416人;長崎:1021人)と女性6196人(広島:4602人;長崎:1594人)の 合計9633人である。被ばく群は被ばく線量推定値がゼロより大きい 5514人、非被ばく群は被ばく線量推定値ゼロの 4119人である。TC値に影響を及ぼす可能性のある疾患ありと診断された対象者は除外した。
特例として成長曲線モデルを含む Laird および Ware の混合効果モデル(Biomerics 38:963-74, 1982)を用いて、モデル化とパラメータ推定を行った。成長曲線法の目的は、長期間にわたって得た連続測定値の変化の経時的パターンの特性を明らかにし、このパターンの変化を引き起こす可能性のある因子を調べることである。この方法は、幾人かの個人でなく、特定の一個人の連続観察値が平均値および分散をもつ正規分布を示し、また年齢、身長、体重などの特定の独立した(成長に関連した)変数と多少関連があるという仮定に基づいているが、それ以外は通常の回帰技法と同じである。一個人の連続測定値の非独立性も検討する。i 番目の対象者の場合、その人が受診したji 回の成人健康調査検診から得た測定値を代表するものとして、この従属変数を以下のように示す。
![]()
ただし、yi はTC(の自然対数)の一連の値である。対象者i におけるyij の成長モデルはその人の年齢および肥満指数(BMI)と関連があると思われる。この場合BMI = (体重 ÷ 身長2)× 100である。
すなわち、
![]()
となる。
各対象者には、それぞれの成長モデル、すなわち数式(1)および成長パラメータセット β=(β0i,…,β5i )があてはめられる。しかし、各対象者はまた、同様の対象者から構成され、独自の成長曲線ならびにパラメータ β=(β0,…,β5)を持つ集団の確率的観察事例とみなされる可能性もある。これは、成長曲線を設定した縦断的データの解析に使用される変量効果モデルと呼ばれる。成長曲線解析の目的の一つは、このような副次集団を区別する因子、すなわち、成長パラメータと成長曲線の全形状を変える因子を同定することである。この解析では、都市、性、出生年から1945を引いた年(出生年*)および1986年線量推定方式(DS86)に基づく放射線量などの因子とそれらの相互作用を調べるが、これらの因子はβ値を修飾することにより集団の成長曲線に影響を与えるかもしれない。
結果
TCの推定成長曲線のパラメータは、固定効果として都市、性、出生年*、都市×性、都市×出生年*、性×出生年*、都市×性×出生年*および線量×性を含む。性を含まない線量の係数はすべてゼロであり、このことは放射線の影響は女性のみに認められることを示している。放射線の影響を除いたTCの経時的傾向を示すために、TCの成長曲線のパラメータである線量にゼロを代入して調整した。TCの期待値を算出するために、BMI成長関数から予測したBMI値を用いた。
このモデルは、多数の交互作用を含むが、ここではその詳細については示さない。しかし少なくとも、年齢に伴うTC値の変動は、性、居住地および出生年により修飾されると言える。その変動をもっと詳細に記述するには図で説明する必要がある。
性および出生年のTC成長曲線に及ぼす影響
図1. は、1910年、1920年、1930年および 1940年に出生した広島の男女の 予測TC値を示す。TC値は年齢と共に増加した。最大の変化が起こったのは若年女性対象者で、28年間にわたる平均的増加は 約70mg/dL であった。一方、変化が最も小さかったのは高齢の男性で、同一期間の平均的増加は 20mg/dL 強であった。長崎の対象者の方が変化が幾分小さかった。両市とも、TC値の増加率は、男性では年齢と共に次第に低下したが、女性では 60歳まではほとんど一定であった。TC値の性差は、40歳未満では小さかったが、加齢と共に増加した。
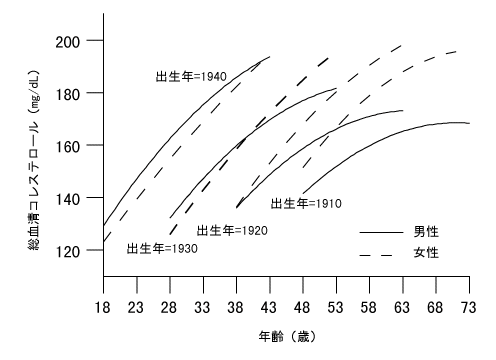
図1. 広島の男性および女性のコレステロール成長曲線。
1986年線量推定方式に基づく推定値ゼロの人の予測曲線。予測肥満指数成長曲線を用いた。
特定の年齢のTC値は、出生が遅い人の方が高かった。10年間隔で示されたコホート効果は出生が遅い人(例えば、1930年と1940年)の方が大きく、平均的な差は 20mg/dL以上 であった。しかし、出生が早い人(例えば、1910年と1920年)の平均的な差は 約10mg/dL であった。10年の間隔を有する出生コホート間のTC値の差は男女とも同じように思われた。
居住地のTC成長曲線に及ぼす影響
C値は、男女とも一貫して長崎の居住者よりも広島の居住者の方が高かった。出生コホートおよび性のTC値に及ぼす影響は両市とも同じであった。
BMIの変動がTC成長曲線に及ぼす影響
BMIは、一般的に男女とも、男性は60歳ころまで、女性は60歳代半ばまで年齢と共に増加し、その後は減少する傾向があった。
BMIの変動は一般的にTC値を増大させるよう影響したが、調査期間中のBMIの変化ではTC値の変化のごく一部しか説明できなかった。
放射線の影響
前に述べたように、放射線の影響が認められるのは女性だけである。この放射線の影響を調べるために、女性(n = 6198)に関するデータのみを用いてTC成長曲線の簡略モデルを評価した。この簡略モデルにおいては、放射線の影響は非常に有意であった( = 42.80、p < 0.00001)。次に、線量と出生年*の交互作用を考慮に入れると年齢の異なる女性の放射線影響が変わるかどうかを調べた。検定の結果は有意ではなく( = 4.07、p = 0.67)、これは被爆時年齢によって放射線影響に変化がないことを示している。
図2. は、1910年、1920年、1930年および1940年に広島で生まれ、DS86線量推定値が0Gyまたは2Gyの女性のTC予測成長曲線を示す。TC値は被ばくした女性の方が被ばくしていない女性よりも高く、その差は年齢と共に多少増加するが、65歳を過ぎると減少した。
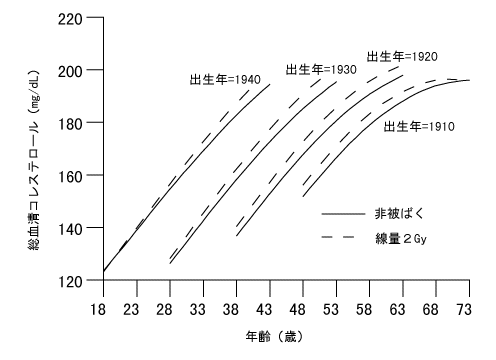
図2. 広島の女性の総血清コレステロール成長曲線、被ばく線量別。
該当する放射線レベルの予測肥満指数を用いた。
1Gy当たりの差が最大なのは 48歳ごろで、その差はわずか 約2mg/dL であった。1930年生まれの広島の非被ばく女性の場合は、BMIが 0.203とすると 48歳の時のTC値の 95%信頼限界は、184mg/dL および 187mg/dL で、点推定値は 185mg/dL であった。被ばく線量 1Gyの女性の同値は 186mg/dL および189mg/dL、点推定値は 187mg/dL であった。被ばく線量 0Gyおよび 2Gyの成長曲線の形状は出生年で差があるようだが、これは、様々な出生コホートでTC値を測定した時の年齢が異なることが原因であって、被爆時年齢によって放射線影響に差があるからではない。
考察
成人健康調査対象者についての今回の調査は、アジア人集団を対象とした数少ない大規模な長期調査の一つである。成人期のTC値を数世代にわたって観察した結果、成人健康調査対象者に認められたTCの増加は、アジア人以外、例えば北米の集団を対象とした大部分の縦断的調査で認められたTC値の変動よりも大きかった。TCの急速な増加およびTCに及ぼす強力なコホート影響は、世代ごとに変化しかつTCプロフィールの悪化の原因となる行動、生活様式および環境に関連した因子の影響が経時的に強くなってきていることを示唆している。
栄養に関する詳細な情報は、我々の調査では得られなかったが、日本人の食習慣が、特に都会で急速に「欧米化」していることは明らかである。(1983年から1985年まで行われた成人健康調査における郵送栄養調査によると、脂肪摂取量が長崎よりも広島の方が多いが、これによってTCの都市間差が説明できるかもしれない。)
本調査の女性対象者のTC値に放射線の影響が認められるのは、放射線に被ばくした女性に早期閉経が認められ、そのためTC値の増加が加速されるためではないかと考えられる(長崎の女性における早期閉経に関する報告については、早田およびJ Cologne著のRERF Update 5(2):3, 1993[広島医学1993年11月号、放影研欄192に訳文掲載]を参照のこと)。
本調査で得られた所見は、放射線被ばくに関連したTC値の増加が、被ばく女性における冠動脈性心疾患による死亡率の増加の一因となっていることを示唆している(児玉和紀によるRERF Update5(4): 3-4, 1993[広島医学1994年5月号、放影研欄196に訳文掲載]、清水らによる放影研業績報告書2-91およびRadiation Research 130:249-66, 1992を参照のこと)。