初期の長崎研究所
初期の長崎研究所(その一)
ABCC長崎研究所 主任医師 James N. Yamazaki (1949-1951年)
今も継続しているABCC-放影研調査プログラムの展開に向けて
1940年代終わりの2年間を若い小児科医はどのように過ごしたか。

左から、筆者、Warner Wells(臨床部1950-1952年)、
浜田道紀(小児科1950-1953年、ABCCの医師募集の広告に応募した唯一人の日本人)
広島・長崎の子供たちの健康調査の実施が検討されていることを初めて知ったのは1948年の1月のことであった。ワシントンDCでの学術会議(NRC)の会合から戻ってきたCincinnati小児病院のAshley A. Weech院長が、原爆医療に最初から参加できる機会があるのだが、今計画中の調査活動に加わる気はないか考えてみるようにと私に打診された。
3月、学術会議の原爆傷害に関する委員会(Committee on Atomic Casualties, CAC)のHerman Wigodsky博士は、手紙の中で「子供たちの慎重な調査と評価がプログラムの主要部分となるであろう。さらに、あなたが関心を有する特別の問題を調査する機会が多くあることは明らかである」と書いている。
さらに手紙は「任期は最低18カ月。委員会はこのプロジェクトが日本で最低10年間は継続すると信じ、できれば50年は継続することを望む。従って、当グループの長期雇用の可能性は無限である。
.....FBIおよび原子力委員会による人物保証が雇用の条件である」と続く。
1948年9月には、私はABCCに参加することを決め、 CACのPhillip Owen理事は、私がCincinnati小児病院のJoseph Warkany博士から準備のための研修指導を受けることを承認した。Warkany博士は、それまでの10年間、食事制限などの環境要因が哺乳類の胎児の奇形を引き起こしうることを系統的研究により証明され、その1年前には、妊娠中に放射線照射を受けたラットに奇形が見られることを報告しておられた。(1930年代初頭から、妊婦の骨盤への治療用放射線照射は子供の中枢神経系異常および目の奇形をもたらす恐れがあるので中止されていた。)
1949年4月、Owen理事は日本での私の任務は広島・長崎の子供たちの先天性奇形に関する調査になるであろうと言われた。その間に、私はJames V. Neel博士に会い、進展中の博士の遺伝プログラムと小児科医のかかわりについて説明してもらい、納得していた。 (RERF Update 1[4]:7-9, 1989; 2[3]:6-9, 1990)
日本へ行く途中、カリフォルニア大学ロサンゼルス校に新設された医学部のStafford Warren学部長を訪ねるようCACに指示された。Warren博士は、原爆後数週間以内に広島と長崎を視察しておられた。* 博士は、後にABCCの最初の調査団の一員となられた東京大学外科教授の都築正男博士との暖かい交流をはじめ、博士の経験をいろいろと語ってくださった。 (RERF Update 1[4]:7-8, 1989; 3[4]:12-3, 1991)
*当時、Yamazaki氏はWarren博士がマンハッタン計画の医務主事であり、1945年7月16日にNew MexicoのAlamogordo近くで爆発させたTrinityを目撃した2人の医師のうちの一人であったことを知らなかった。また、 Warren博士は1946年のOperation Crossroadsと呼ばれた核実験の放射線安全主任も務めた。
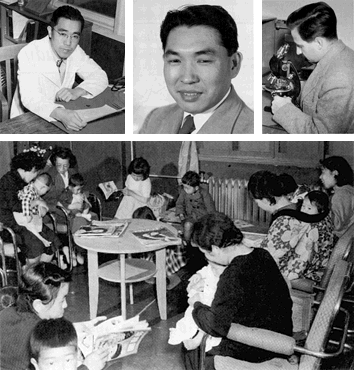
左上から、Wataru Sutow(小児科1948-1950年)、著者(1950年)、Wayne Borges(小児科1949-1951年)、長崎研究所の待合室
不調な出足
1949年9月、妻と生後5カ月の息子を連れ横浜に着いて分かったことは、手紙で確約されていたにもかかわらず、広島に適当な住居がないということだった。私の家族は阿賀に住居が見つかるまでの数週間東京に留まった。私の方はそのまま広島へと向かい、そこで格別気の合う人たちに会った。それは遺伝学者のWilliam Schull博士、小児科医のWayneおよびJane Borges博士夫妻とWataru Sutow博士だった。
Sutow博士も日本に到着してすぐ憂き目を見た。地区を統治していた英連邦占領軍(BCOF)が日系アメリカ人の子弟がBCOFの学校へ入学するのを認めなかったため、博士がABCCに在職した2年間、博士のお嬢さんは学校へ行くことができなかったのである。** 戦闘を経験した兵士であり、またドイツ軍の捕虜にもなった自分としては、学術会議が支援する任務に携わる者がこのような人種差別にあっていいのかと愕然とし、また怒りを覚え、ABCCの最初の二人の所長、Carl Tessmer中佐(1948-1951年)とGrant Taylor博士(1951-1953年)に意見を述べた。
**1949年3月5日付けのBCOFの公式メモには、アメリカ人職員がBCOFのレクリエーション施設や店などの関連施設を使用するための許可条件が記されている。米軍の制服を着用していない場合、日系人はほとんどのBCOF施設への立ち入りを許可されていなかった。
長崎での任務
数週間後、TessmerとTaylor両氏から主任医師として長崎に配属されることを告げられた。ワシントンDCの話し合いでは一切そのような話はなかった。私にはその気がないこと、管理職の経験がないこと、また、ただ小児科学の調査をしたいがために日本にいることなどを理由に挙げて異議を申し立てた。この転属が広島・長崎の子供たちに終生かかわることになる私の人生の転機となるとは当時の私は知る由もなかった。
11月になりTaylor博士に長崎を案内してもらった。長崎では取得したばかりの桜馬場町の会館を訪ね、改築計画が計画中の調査プログラムの内科と検査室のニーズを満たしていることを確認した。既存のABCCの調査はあちこちに散らばって行われていた。Robert Kurata博士は、離れた仮施設から遺伝プログラムを指導していた。ABCCの医師や看護婦は長崎大学医学部臨床部の臨時施設の一つであった新興善病院(原爆前は小学校であった)の一隅を使用していた。また、ABCCの記録文書は魚市場にあった事務所に保管されていた(RERF Update 1[4]:7-8, 1989; 2[3]:6-9, 1990)。会館を取得したお陰で、その改築前であったけれどこのような作業を統合することができた。
長崎にたった一人のアメリカ人医師
長崎に赴任した際、私は幾多の研究外の仕事を引き継いだ。ABCCが採用した医学部新卒医師のための講師、ABCC職員およびその地域に駐屯していた米国陸軍分遺隊とその家族の掛かりつけ医師まで、時には夕方往診を頼まれることもあった。私が切望していた放射線影響の研究は1年以上も後回しになってしまった。 (RERF Update 1[4]:7-8, 1989)
当時の我々の主目的は、広島のABCCの運営に、長崎の足並みを揃えることだった。広島では、内科医および小児科医が必要人員いて、血液学者1人、研究所長1人、病理学者1人、婦人科医1人、放射線科医1人、外科医1人、それに統計学者、管理職、技師、看護婦、検査技師など必要定数を揃え進行していた。比治山の上には常設施設が建築中であった。

愛宕町のYamazaki家で開かれたクリスマスパーティーに参加したPaul Takao、浜崎和雄 、 Phyllis Wright、築城士郎、浜田道紀をはじめ遺伝プログラムの多くの医師たちとABCCの職員。 前列左から4人目が筆者の妻Aki Yamazaki
初期の長崎研究所(その二)
ABCC長崎研究所 主任医師 James N. Yamazaki (1949-1951年)
日常業務の執行態勢を整えるためには数多くの事務処理とABCCと長崎市民との間に相互利益をもたらす関係を醸成することが必要であった。

1951年5月筆者の送別会のため茂木に集まった長崎市医師会会員。
腰をかけている左から、イマムラ ハラキチ、筆者、有富重国、Stanley Wright、大須賀越、
立っている左から、井手政雄、品川喜八、柴田精朗、林田浦治、林田シュンスケ、朝永雄三
地元との関係を築くための第一歩
長崎市民の間に原爆傷害調査委員会(ABCC)に対して疑念があるということを噂で聞いたので、ABCCの医学的使命について緊急に地元の医師会と官庁職員に説明することが大切であると感じた。さらに、原爆の後どうなったのかについて説明を受けていなかったので、長崎の人々の体験を学ぶことが自分に課せられた義務であると思った。私は最低限の日本語しか話すことができなかったので、ABCCの通訳/翻訳員の浜崎和雄氏に最初の地元との接触を手伝ってもらい、一緒についてきてもらった。
長崎市警察本部警部、原爆直後について語る
出口勝治主任は、原爆が炸裂した時は長崎防空襲隊の副隊長だった。彼の話を聞き、1945年8月9日の出来事について初めて実状を知ることができた。
勝山小学校内に設けられていた派出所を大勢の被爆者が通り過ぎて行くありさまをかなり詳細に語ってくれた。派出所は爆心地から約3000mのところにあった。歩ける人は金毘羅の山を越え西山へと向かった。他の出口はすべて火に包まれていたからである。市全体がことごとく被害にあった。絶望と混乱が蔓延していた。怪我人があまりにも多すぎたため救援を2週間も待たねばならない人もいた。火葬や埋葬も同じくらいの期間続いた。近隣の町や村の人たちは被爆者を助け、一カ月以上も食料を提供した。人口の大部分が市外へと逃れていった。
長崎県知事
杉山宗次郎県知事は、当初から非常に暖かく私を迎えてくださり、夕食会で多くの県職員に紹介してくださったので意見の交換もスムースに進んだ。また、知事はたくさんの社会的行事に我々を招待し、それを通して長崎の生活について教えてくださった。こういった会合のために私が夜家を空けることを妻Akiがだんだん面白くないと思うようになったと伝え聞いた知事は、魅力的な奥方を妻のもとへ送ってみえた。一度など、夫人はAkiに大変美しい着物を持ってきてくださった。
長崎大学医学部
長崎大学(長大)医学部とABCCの間には大変暖かい友好関係が生まれた(RERF Update 2[1]:9, 1990)。医学部の建て替えが始まったばかりの時に、浦上で影浦尚視医学部長と調 来助外科教授に初めてお会いした。一番初めに建て替えられる建物にABCCは部屋を提供してもらうことになり、そこでSam Kimura博士(ABCC臨床部 1949-1950年)が白内障の調査をすることになった。長大の広瀬金之助眼科学教授はすでに白内障調査にたずさわっておられた。
ABCCの剖検は、長大で進行中の病理・解剖プログラムに従っていた。そしてABCCの医師は日本の医師免許を持っていなかったので影浦学部長がそのつど剖検許可書に署名をすることに同意された。ABCCの剖検は浦上で長大の剖検執刀医によって行われたのである。
学部長は、ABCCが採用した若い医師–同医学部を卒業したばかりの医師–にアメリカ式医療を指導して欲しいと依頼してこられた。それに応えて、私と広島から訪れたABCC来所研究員が定期的に講義を行った。そして、大学当局はABCCの小児科の医師、瀬戸口匡彦(1949-1951年)と高尾篤良(1948-1952年)が大学の籍を継続できるようにしてくれた。
その後、調教授がABCCのプログラムを長大部長会議で説明するようにと私に勧められた。私は通訳の浜崎氏を同伴して行ったのだが、調教授は私が日本語で話す方がふさわしくまた喜ばれるであろうと言われたので、私は生まれて初めて日本語で講演をした。私が話したような日本語は聞いたことがないと思われたであろう。私が話し始めると皆の真剣な表情が柔らぐのが分かった。
私の要請で医学部の被爆者による討論会が1950年6月7日に開かれ、広島からKimura、William J. Schull、武島晃爾博士が参加した。その後調教授は私との会話の中でご自身の経験についてさらに語ってくださった。博士の報告書The Medical Survey of the Atomic Bomb CasualtiesはABCCに提出され、後に英訳され出版された(Milit Surg 113:251-63, 1953)。事実、これは原爆の医学的影響に関する初めての要約報告だった。日米合同調査団の報告書はその翌年の1951年4月になり初めて発行された(6巻中、最終巻は1954年11月30日に機密扱いを解かれた)。合同調査団の報告書が発表されるまで、私と話をしていたABCCの医師たちはその内容について何ら説明を受けていなかった。
長崎医師会
医師会の総会、夕食会、小児科部会、産科部会でABCCのプログラムについて説明し、米国における医療に関して多大の興味が示された。
日本助産婦・看護婦協会長崎支部
会長の村上テイさんが、長崎で出生した新生児の90%-95%についてABCCに報告した106人の助産婦を代表していた(RERF Update 2[3]:6-9, 1990)。彼女は遺伝プログラムの目的を理解し、建設的な意見を出された。助産婦の会議は定期的に開かれ、Schull博士は何度かこの会議に出席された。
西山地区放射性降下物調査
1950年3月、Tracer Labsが西山地区の貯水池の上流における残留放射能について調査した。放射性試料がわらぶき屋根および貯水池の沈泥から収集された。彼らの短期間の滞在中、調査員たちに同行し、爆弾の降下物について学んだ。その調査結果は我々には報告されず、当時のABCCの報告書にも掲載されなかった。
朝鮮戦争
1950年6月の終わり、朝鮮動乱が始まった。長崎から飛行機でほんの10分の距離での動乱であるので、長崎研究所を閉鎖すべきかどうかといった憶測がかなりあった。長崎・佐世保に駐屯していた兵隊がまず送られたが、同地区から行った兵士は一人も戻ってこなかった。頼まれて、海上で猛爆撃を受けた時に負傷した商船の船員を治療するために波止場へ急いだこともある。
1951年の初め、戦いが小康状態となった時、太平洋上陸部隊が港に寄港した。我々は司令官と隊員に原爆が引き起こした結果について簡単に説明するように要請された。
そのほかに思い出すこと
1950年9月、台風のまっ最中、Stanley WrightとPhyllis Wright (小児科1950-1952年)が長崎に赴任してきた。これによりアメリカ人研究員の数が3人に膨れ上がった。会館の改築もほぼ完了し、実験室職員の訓練もほぼ終了していたので、2人の赴任は時宜にかなっていた。
そのすぐ後、呉の遺伝プログラムの閉鎖に伴い細胞遺伝学者のMasuo Kodani博士(遺伝学部1947-1955年)が長崎に赴任してきた。博士は長崎の遺伝プログラムを指導し、細胞遺伝調査を引き続き行った。 Stanley Wrightが職員の健康管理を担当することになった。結核のために職員の10%が入れ替わっていたのでこれには十分な注意を払わなければならなかった。
1950年10月、桜馬場町のABCCの診療所で患者の検診を開始した。9カ月児の20%を再検診したので、数カ月のうちに患者数は広島と同じくらいになった。Phyllis Wrightは、1948年にW. W. Greulich博士が開始した学童の成長発育調査を担当することになった。
長崎の女性の妊娠終結に関するPE57調査計画が、その実施を目指して検討された(JN Yamazakiら、J Cell Comp Physiol 43[suppl 1]: 319-29, 1954)。小児科のGeorge Plummer博士(1950-1952年)の書簡には、PE57調査は広島でも行うべきであると書いてあった。
Kimuraと広瀬による放射線誘発白内障に関する眼科調査は、爆心地から1000m以内にいた被爆者600人を対象として行われた。その後、Paul Fillmore博士(臨床部1949-1951年)がこの被爆者グループを追跡調査している(PG Fillmore, Science 116:322-3, 1952)。OP46と呼ばれた175人の子供を対象にした調査が1951年3月に終了したが、この調査結果が発表されたのかどうか知らない。
1951年の初め、米国原子力委員会の生物医学部のJohn Bugher副部長とカリフォルニア大学ロサンゼルス校のJohn Lawrence医学部長が長崎に1週間滞在してプログラムの検討を行った。
6月、妻の病気のため私は予定を数カ月繰り上げて長崎を去った。

1950年秋、ABCCで開かれた長崎助産婦協会会議
助産婦の後方に立っているのが、左から Stanley Wright、小谷万寿夫、筆者、通訳の浜崎和雄
この記事は RERF Update 4(3):8-9, 1992に掲載されたものの翻訳です。
前半(その一)はRERF Update 4(3):8-9, 1992に、
後半(その二)はRERF Update 4(4):8-9, 1992に掲載されました。

